東京国分寺市恋ヶ窪、ちょっと粋な名前を持つこの台地を源泉とした野川。ちょろちょろとした湧き水の流れは、やがて川となり東京の武蔵野を抜け多摩川に合流する。
人は川の流れに人生を重ね見ることがある。緩やかなれど決して流れは止まらない。湧きだした流れは蛇行し、石にぶつかり、魚と戯れ、鳥に餌を与え、雨水を仲間に受け入れ、それは、人が止めることのできない人生の歩みに似ている。
野川は多くの人々の様相を映してきた。そして、その流れは人の縁を繋ぐ不思議な世界へと続いている。
その、時の狭間で、野川の小さな奇跡が始まる。
プロローグ
虎狛橋の欄干に両肘をつき、滝のように流れる汗は頬を伝って顎の先から川に落ちた。公平は川沿いに咲く満開の桜の花を吸い込むかのように大きく深呼吸をした。この時期、野川は数百本のソメイヨシノが春爛漫と咲き誇り、春の訪れを感じさせる。早朝の春風が心地よく公平の顔を撫でた。川のせせらぎに合わせて緩やかに揺れる桜を眺めながら公平は母和美のことを思い出していた。
「今年の桜も満開、きれいだねぇ」
和美はゆっくり歩きながらこれが見納めと悟ったように呟いた。
「そうね、ここの桜は調布市民の誇りだわ」
琴乃は母と腕を組みながら笑顔を見せた。
「大袈裟だな、お前は」
「ふん、お兄ちゃんは感性が乏しいのね。ねぇ母さん」
琴乃は母の腕にしがみつき顔を摺り寄せた。公平は天真爛漫に話す妹が健気に思えた。
その年の一月、末期癌と宣告された母の余命を知り、兄妹はできる限り母と過ごす時間を作った。この日、病院から外泊を許された母は週末の二日間を過ごそうと自宅に戻っていた。まだ人が少ない土曜の早朝の川沿いを三人は散歩していた。朝陽が川面に反射して眩いばかりに輝いていた。せせらぎが三人の耳に優しいリズムを与えた。ときどき鯉が跳ねる音や風に揺れる川岸の草の音、日頃気にもとまらない音が今は思い出を刻むように感じられた。
「誰が植えたのかしらね。この桜並木。こんなにきれいに咲いて。植えた人に感謝しなきゃ」
「そう言えばそうだな。いつからここで咲いているのかな」公平は毎年咲く桜についてそんなことを考えたこともなかった。
「来年はもう見られないかもしれないね」
「母さん、何言ってんのよ。来年はお兄ちゃんのお嫁さんも一緒に見られるよ」
「あんたは嘘が下手ね。顔に出てるよ」
和美は笑って娘の言葉に返した。
「そんなことないって! 病院の先生もよくなってきたって言っているよ。大丈夫!来年も絶対に見られるわ」
琴乃は自分に言い聞かせるように川面に目を移して言った。内心は泣き出しそうな感情を必死で抑えていた。和美は娘の優しさをありがたく、そして素直に育ったことに安堵と喜びを感じていた。自動車の修理工場を営んでいた夫浩司が心筋梗塞で急死した後、抱えていた借金のため工場を手放し、女手一つに二人の子供との生活がのしかかってきた。父親がいないからだらしがないと世間から言われないように厳しく愛情を持って育てると心に決めた。当時、公平はまだ小学二年生、琴乃は二歳になったばかりだった。和美は昼夜を問わず働いた。幼いながらも公平は母親の苦労を感じて育った。公平は家の貧しさを感じさせない明るい性格で小学校時代を通じてクラスの人気者だった。成績も良く、いつも笑顔を絶やさない他人への気配りができる子供だった。しかし、それは母親に心配をかけさせないために装ったところが大きかった。中学に上がると母を助けるために早朝の新聞配達を始めた。和美は我が子に申し訳ないと思いながらもそのわずかな収入に助けられた。琴乃は頼もしい兄を幼い頃から尊敬して育った。
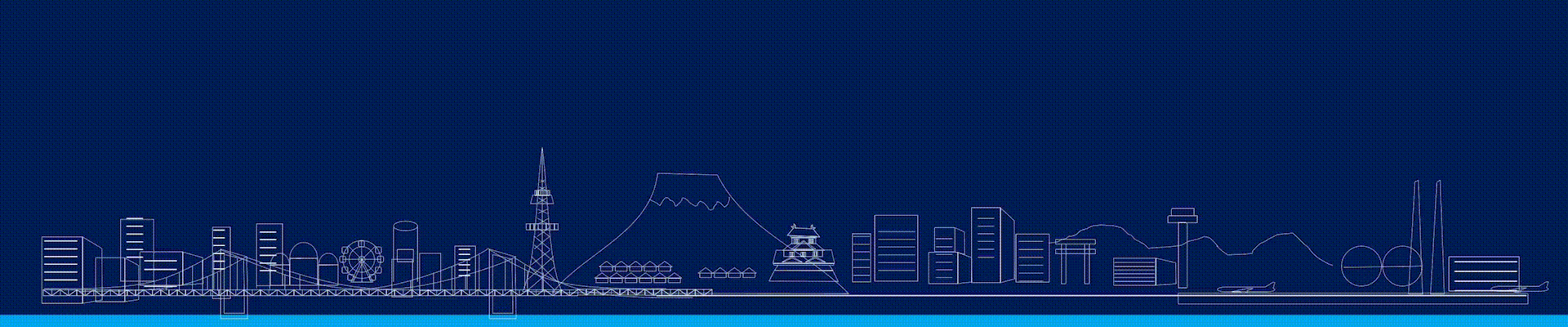

Login to comment
サインイン