始まりの風
虎狛橋が折り返し地点と決めていた。公平はこの日もいつも通り、早朝のジョギングをして、この橋の中央の欄干に両手をつき、屈伸をして大きく深呼吸をした。野川のせせらぎは今朝も公平に爽快感を齎した。大きく背を反らし青い空に顔を向けた。
「ん? 何だ、あれ?」
一瞬、ドップラー現象のようなビューンという音が聞こえた気がして目を凝らした。二機の飛行機が空中戦をしているシーンが飛び込んできた。公平は目を大きく見開いたが、ほとばしる汗が目に入り、その画像は途切れた。人差し指の背で汗を拭い、再度目を開けると、そこには二羽の鳥が空中で戯れていた。なんだ鳥か。
その時だった。川面から清々しい風が吹き上げた。それは優しくまるで身体の中に溶け込んでくるような感じのする風だった。
朝陽が川面に反射してキラキラと輝いていた。公平はいつものように川に向かって静かに手を合わせた。今日も一日よろしくと祈りながら。何がよろしくなのか、公平自身も具体的なことがあるわけではない。ただ母と最後に散歩をしたこの川で手を合わせることがいつの間にか習慣になっていた。心のどこかで母への思いが、ここにくれば届くのではないかと思ったのかもしれない。
公平は復路を走り始めた。
小さな公園の脇を過ぎようとした時だった。
「昭夫君!」と驚いたような声がした。足を止め周りを振り返るが誰も見当たらなかった。その声は明らかに公平に向けてかけられたものだった。もう一度声のした方向を窺うと、そこにはベンチに座り、身を乗り出すようにした一人の老婆が公平を見つめていた。
「昭夫君、昭夫君なのね! 無事だったのね。佳子ちゃんは? 佳子ちゃんも無事なの?」
老婆は公平にすがりつこうとしてベンチから落ちそうになった。公平は慌てて駆け寄り支えて言った。
「いやいや、おばあさん、違います。人違いですよ」
公平は優しくその老婆の肩を抱くようにしてベンチに座り直させた。
老婆はしばらく公平の顔を見つめていたが、はっと気が付いたような表情になり、そして大きな溜め息を吐きながら言った。
「そうね、そうだわね。昭夫君じゃないわね。ごめんなさいね、大きな声を出してしまって」
「いいえ、僕が誰かに似ていたのですか?」
「ええ、そうなの、私の教え子に本当によく似ていたものだから。本当にごめんなさい」
公平は隣に腰掛けるようにして改めてその老婆を観察した。パジャマの上に袢纏を羽織り、素足に左右異なったサンダルを履いていた。肩からちょっと長めの紐を斜め掛け、その先には地味な色合いの格子柄の巾着がついていた。春とはいえ、早朝はまだ肌寒い。素足では冷えるだろう。公平はその老婆が普通ではないように思えたが、それでもきちんと整えられた真っ白な髪がどこか品の良さを感じさせた。
「おばあさん、何か教えているの?」
「昔ね、調布国民学校で教えていたの。代用教員だったのよ」
「国民学校? ダ・イ・ヨ・ウ教員って、何の学校ですか?」
老婆はちょっと不思議そうな顔をしたがすぐに優しい笑顔で言った。
「あなたいくつ?」
「二十八です」
「若い人にはあの戦争はもう歴史で習う一コマに過ぎないのね」
「戦争って世界第二次大戦のことですか?」
「そう、太平洋戦争よ。昭和十九年の秋に代用教員になったの。まだ女学校を卒業する前だったんだけど、男の先生の多くが戦地に赴いたから女学校の生徒が代用教員になって小学校に派遣された時代だったのよ。今の若い人には分からないかもしれないわね。あの戦争は、幼い子供たちが経験するにはあまりにも残酷なものだったわ。私は五年生の担任になって、その時の教室にいたのが昭夫君。妹が一人いて、とてもしっかりとしたお兄ちゃんだった」
えっ? 俺がその時の小学生に似ているのか? このおばあさん呆けてるのかな……公平は心の中で呟いた。
「昭和二十年二月十九日、米国による東京への空襲は一段と酷くなった。たくさんの人が焼き出され、この辺りも米軍の飛行機が飛び回った。それに応戦するために、調布飛行場から轟音とともに次々と『飛燕』が飛び立って、米国の戦闘機に向かっていく様子を私は子供たちと防空壕の中でわずかな隙間から見ていたの。子供たちの小さな肩は震えが止まらないの。でもみんな必死で我慢をしていた」
「飛燕?」
「そう、日本軍の戦闘機の名前よ」
「調布の空で戦闘機の空中戦があったのか」と呟くように言いながら、公平はさっき橋の上で見上げた空のことを思い出してはっとした。あれは飛燕の幻?……だったのだろうか。
老婆は視点を定めず、遠い過去をたどって話し始めた。
「ちぃ先生、怖いよぉ!」
空中戦の轟音が防空壕の中まで響いていた。子供たちは青ざめ、小さな手は硬く握られていた。
「大丈夫、先生にくっついていなさい」
千鶴は低学年の子供たちの肩を抱いて励ました。
「ちぃ先生、めだかの学校は大丈夫?」一年生の女の子が聞いた。
「大丈夫よ、皆も頑張っているんだから、めだかたちもきっと頑張っているわ。」
「ちぃ先生、川の石をどけてあげないとめだかが逃げられないよ。」
子供たちは先生と一緒に石を積み上げて作った生け簀のめだかを心配した。
「めだかは絶対に大丈夫よ、石の間を抜けて逃げてるわ」
「じゃあ、どうして今まで逃げなかったの?」
「それはみんなと遊びたかったから。戦争が終わったらまた、めだかの学校を作りましょう。だから、みんな頑張るのよ」
千鶴は子供たちを励まし続けた。
外の空中戦の音が恐ろしく響いていた。子供たちは小さな手で耳を塞いで恐怖に耐えた。
「お兄ちゃん、お母ちゃん遅いね」一年生の佳子が心配そうに言った。
「母ちゃんの工場はしっかりした建物だから心配するな。きっと、もうすぐ帰って来るから」
昭夫は妹の頭をそっと撫でた。しかし、外の情況を理解できる昭夫の心の内は張り裂けんばかりだった。
空中戦の轟音は続いた。そのうちに今までの轟音とは違う爆音が聞こえてきた。六、七機の見たこともない黒い大きな爆撃機が編隊を組みながら青空に現れた。飛燕が応戦したが、調布飛行場を狙った爆弾の投下が始まった。爆音と振動は吐き気がするほど腹の底まで響いた。防空壕の天井からバラバラと小石が落ちた。子供たちは泣き叫んだ。千鶴は祈った。ここに落とされれば子供たちは死んでしまう。どうかここには来ないで。
その爆音は昭夫の我慢も打ち砕いた。
「先生、母ちゃんがまだ帰ってこないからちょっと見てくる」
昭夫は震える妹を千鶴に託すようにして防空壕の外に飛び出した。
「駄目! 出ちゃ駄目!」
千鶴は必死で叫んだが昭夫は聞かなかった。その叫びを聞いて奥にいた教師の都築が声を出した。
「千鶴先生、どうしましたか!」
「あっ、都築先生、昭夫君が外へ出てしまって」
「なんだって!」
都築が昭夫を追いかけて防空壕の扉を開けようとした時、二発目の爆弾が落ちた。
「昭夫君!」
千鶴は叫んだ。地響きとともに扉に無数の粉塵が当たる音がして、とても扉を開けられる状態ではなくなった。千鶴は唇を噛んで泣きたい気持ちを必死に抑えた。今私が泣いたらこの子たちが余計に怖がってしまう、そう思い、気丈に振る舞った。
「みんな、泣かないで。大丈夫よ」
千鶴は昭夫の身を案じ、いても立ってもいられない衝動に駆られた。
昭夫と佳子の母親は軍服の縫製工場で働いていた。空襲警報のサイレンが鳴り響き、工場で勤労奉仕をしていた人々も何人かがこの防空壕に逃げ込んだが昭夫と佳子の母はそこにいなかった。昭夫と佳子は母を呼んだが防空壕内で返事を聞くことはなかった。
防空壕から飛び出た昭夫が見たものは変わり果てた調布だった。信じられないような光景がそこに広がっていた。呆然とした昭夫だったが、我に返って、母ちゃん、母ちゃんはどこだ、心の中で母を呼んだ。
母ちゃん!
母が勤める縫製工場に向けて昭夫は走った。工場までは十分ほどの距離だった。走り始めたその時、後方で耳を貫くような爆音と同時に爆風が起こり、前に押されるように膝をついた。幸いコンクリート壁が昭夫を爆弾の直撃から守ってくれた。空を見上げると米軍機が東の方向に飛んでいくのが見えた。
やがて米軍機は見えなくなり、静寂が戻った。「母ちゃん。」昭夫は立ち上がると再び走った。『母ちゃん、母ちゃん』昭夫は心で叫びながら流れ出る涙を拭うこともなく走った。工場が見えた。飛び込むように工場の中に入った。
「母ちゃーん!」
工場内には国民服を着た数人の男がいた。
「誰かな、君は?」一人の男が声をかけた。
「俺の母ちゃんいませんか」
「さっきの空襲でみんな逃げたから今ここには誰もいないよ。お母さんの名前は?」
「田所、田所邦子です」
「ああ、田所さんの息子か」
「はい。母ちゃんはどこに行きましたか?」
「工場の防空壕に入るように言ったんだが、田所さんは君たちがいる防空壕に行くと言って、出て行ったんだよ。無事だといいんだが」
それを聞くと昭夫は一目散にまたもと来た道を走った。なんだ、母ちゃんは俺たちのところに戻ったのか。どこで行き違いになったのかな。もうすぐ母に会えると思うと胸が熱くなった。途中、爆撃で壊れた建物の前に何やら人が集まっていた。昭夫が横目でその様子を見ながら先を急ごうとしたその時、昭夫ちゃん! と甲高い声に呼び止められた。隣に住む加藤俊子だった。
「ああ、加藤のおばさん。どうしたの?」
「昭夫ちゃん、お母さんが……、早く来て、早く」
俊子は昭夫の腕を掴むとその人垣の中に連れ込んだ。
「母ちゃん……」
昭夫はそこに倒れている変わり果てた母を見つけた。
「母ちゃん、母ちゃん」
白いブラウスは血で真っ赤に染まっていた。
「田所さん、しっかりして。昭夫ちゃんはここにいるよ」
俊子が昭夫の肩を抱くように話しかけた。
「さっきの爆撃の時に、逃げ遅れて一人立ち竦んでいた女の子を田所さんが覆いかぶさって守ったんだよ。爆風で飛んできた瓦礫が直撃して……」
その場に居合わせた中年の男が顔をゆがめて言った。
「母ちゃん、母ちゃん」昭夫は必死で母を呼び続けた。
その声に反応するように邦子の目が薄らと開いた。「母ちゃん!」
「あ・き・お、佳子を頼んだよ。母ちゃんはいつもお前たちの傍にいるからね。母ちゃんはきれいなお花が咲いているこの川辺にいつでもいるからね」
邦子は昭夫に手を伸ばそうとした。手首がわずかに動いたが昭夫に届くことなく邦子は静かに目を閉じた。
「母ちゃん! 駄目だよー。死んじゃ駄目だよ!」昭夫は母にすがった。
爆音が遠のき防空壕から外に出た千鶴は昭夫を探していた。あちらこちらで爆撃の傷跡に火がくすぶる瓦礫を避けて歩きながら、ある人垣の中に昭夫を見つけた。
「昭夫君……」
「先生ぇ、母ちゃんが、母ちゃんが」
昭夫は千鶴にしがみついて泣いた。そこには血に染まった昭夫の母邦子が横たわっていた。千鶴は昭夫を抱きしめながら目を見開き、心の底から戦争を憎んだ。
その後も米軍機による空襲は頻度を高めた。ある日、飛燕の応戦により一機の爆撃機が墜落した。B29だった。その機体の大きさに人々は驚きと恐怖を感じた。パラシュートで脱出した数人の米国人兵士は憲兵隊に捕らえられたが、数人の兵士が助かることなく墜落した場所に投げ出されていた。
子供たちは初めて外国人を目にした。鬼畜米英と習った子供たちはその米兵を見て驚いた。金髪に青い目、きれいな顔だった。学校で教えられた鬼畜の様相とはまったく違っていた。大人たちはその遺体に向かって「お前たちのせいでこんなになっちまったんだ。コノヤロー!」と中にはその遺体を蹴飛ばす者もいた。そこにいた子供たちは大人のすることを複雑な気持ちでじっと見つめていた。学校で教わるべき人を思いやる心とはまったく違う人間の憎しみを子供たちはどのように理解すればいいのか、そしてそれを誰が教えてくれるのか、千鶴は教育の矛盾に憤りを感じていた。
「人を憎んではだめ。戦争を憎みなさい。同じ人間なの。この人にも家族はいるの。いつか仲良くできる日が必ず来るから」
千鶴は子供たちにそう教えるとそっと手を合わせた。子供たちも千鶴に並んで小さな手を合わせた。
公平はいつの間にか老婆の話に引き込まれていた。そして昭夫がどこか自分と重なるように思えた。
「それで、昭夫君はどうしたのですか? 妹さんは?」
「佳子ちゃんは都築先生が連れて他の子供たちと一緒に無事に防空壕を出たのだけど、昭夫君と佳子ちゃんのお父さんは南方の戦地に出兵して戦死されてね、兄妹二人きりになってしまったの」
邦子は近所の寺に安置され、近所の人たちの手で簡単な葬儀が行われた。
「お兄ちゃん、お母ちゃんがかわいそうだね。きっと痛かったよね。でもお母ちゃん、泣かなかったんでしょ。お母ちゃんはやっぱり強いね。だから私も泣かないよ。強い子になりなさいっていつもお母ちゃん言ってたから。辛い時は笑いなさい、嬉しい時に泣きなさい、って。泣いたらお母ちゃんが心配する」
佳子は流れる涙を小さな両手で顔を洗うように拭い、真っ赤な顔で兄を見た。そして無理矢理な笑顔を作った。その笑顔に、周囲の人たちは泣かされた。
「佳子、母ちゃんはいつでも野川にいる。だから寂しくないぞ。いつでも会えるんだから。最期に母ちゃんがそう言ってた」
昭夫は気丈に妹を慰めた。佳子を勇気づけるために昭夫は必至で泣くのを耐えた。
「野川? そうか、三人で大根洗ったね。あの時、この川のようにきれいな心を持ちなさいって。もし、戦争で離れ離れになったらここに来なさい、お母ちゃんも必ずここに来るからって言ってたね」
「お母さんとよく川に行ったの?」千鶴が尋ねた。
「近所の畑でもらった野菜を一緒に洗いによく行ったんだ。母ちゃんはいつも、川は泥や汚れや悪いことを流してくれるから好きだって言ってた」
昭夫はその時のことを思い出して俯いた。
「お母ちゃん……」
そう呼びかけて佳子は本堂に安置された邦子に寄り添って横になり、甘えるように抱きついた。もう抱いてもらえない母の腕に顔を擦りつけながら。
「昭夫君は本当に妹の面倒をよく見たのよ。しばらく近所の人たちに助けてもらって、私も毎日行って二人の世話をしたの。でも幼い兄妹が二人で生きていくのは限界があるわ。ある日、埼玉の叔父さんが来られてね、二人は連れられて行ったわ。佳子ちゃんは先生と離れたくないと言って泣いていたけど、あの時は仕方がなかったの。二人の寂しそうな目が忘れられない」
千鶴は首を振りながらいまだに二人を行かせてしまったことを悔いるように言った。そしてその後も戦争の悲惨さと終戦後の生活について公平に語り続けた。それは千鶴の人生そのものであった。
「私は二人が無事でいてくれることを願って生きてきた。二人のことは片時も忘れたことはない。叶うなら最期を迎える前に会いたい……。会ってごめんなさいと言いたいの。でももうこの歳じゃ無理ね」
千鶴は二人の顔を思い浮かべて朝の青空を見上げた。公平は胸が詰まる思いだった。
「僕にも妹がいるんです。しかも昭夫君と同じ五つ年下の。今は保育園の先生をしています。僕らも先月、母を亡くしました。僕の母もこの野川が好きでした」
公平は初めて会ったこの老婆に自分のことを話したくなった。
「こんな歳になって恥ずかしいのですが、ここに来ると母がどこかにいる気がするんです。ガキじゃあるまいし、そんなことあり得ないのは分かっているんですが。何だか昭夫君の気持ちが分かる気がします。川に行けば母ちゃんに会えるっていうその気持ちが」公平はそう話した。
「きっと、あなたのお母様もここにいるわ。見守ってくださっているわよ」
老婆は確信を持って、そう言った。
「おかあさん!」
突然一人の女性が少し離れたところから叫ぶように声をかけた。
「なんですか、大きな声で」
「えっ?……分かるんですか?」
その女性は驚愕の表情で駆け寄ってきた。
「おかあさん、私が分かるの?」
「何を言っているんですか、香穂さん。あなたはウチの大事なお嫁さんですよ」と冗談交じりの笑顔で応えた。
「おかあさん……」
涙でそう言うのが精一杯な様子で地面に膝をつき、老婆にしがみついた。
「どうしたんですかぁ。子供みたいに」と老婆は優しくその女性の肩に手を置いた。
「だって、だって……」泣き声で言葉が震えていた。
「あらあら、人が見てますよ」老婆は優しく諭した。
「あのー……」異様な場面に公平が声をかけた。
「あら、ごめんなさい」
我に返ったその女性は涙を拭きながら身を起こした。
「目が醒めたら母の姿がなく、家中どこにもいなくて、玄関にサンダルがないのを見つけて飛び出してきました。近所を探し回っても見当たらず途方にくれていたのですが、よく野川のことだけはときどきはっきりを話すのを思い出して、ひょっとしたらと思って来てみたら、川の向こう側から母らしき姿を見つけて走ってきたんです。母は認知症で……。でも、今は分かるのよね、おかあさん」
その目は希望を取り戻したようであった。
「はいはい、ちゃんと分かっていますよ。でも不思議ね、私はどうしてここにいるのかしら」
千鶴は長い夢から醒めたように改めて周囲を見回した。
「おばあさん、認知症だったんですか? 全然そんな感じしませんでした。とても良いお話を聞かせていただきました」
「そうだったんですか、話を聞いていただいたのですね。ありがとうございます。そのお陰で母の意識がはっきりと戻ったのですね。母はこの一年、昔のことと現実が分からなくなり、次第に言動がおかしくなりました。認知症と診断され私が世話をしています。あっ、申し遅れました、私、菊池と申します。本当にありがとうございました」
「野々村です。野々村公平と言います。おばあさんは千鶴さんと言われるのですね。おばあさんのお話で分かりました。ちぃ先生、いつまでもお元気で」
「ありがとう。あなたもね。若い人がこの平和な日本を守ってくださいね。二度と戦争なんか起きないようにね」
「はい。頑張ります」公平は何だか嬉しくなった。
「また会えるといいわね」千鶴は優しく微笑んだ。
「はい。僕は毎朝、ここを走っていますから」
「そうなの。じゃあきっとまた会えるわね」
「はい。きっとお会いできます」
公平もまた千鶴に会いたいと思った。
ベンチから立ち上がった時、千鶴はふと動作を止め、まるで誰かに言われたように肩に掛けていた巾着の中から小さな御守を取り出した。それは古そうに見えたが、金糸で刺繍が施され、どことなく高貴な感じがするものであった。
「これ、もらってくれないかしら」
「そんな、いただけませんよ」
「私はもう、十分守られたから」千鶴は御守を両手で差し出した。
「そんなだめですよ。これからもその巾着に入れて大事に持っていてください。その巾着、かっこいいですよ」
「この巾着、私が作ったんです。母の着物の余り布を使って。亡くなった父が母に買ってあげた大島なんだそうです。万一、母が迷子になった時にと思って、連絡先とお金を少々入れてあるんです。この御守もいつもこの中に入れて大事にしているんですが、この御守がどういうものなのかは知りません。母に聞いても教えてくれないのです」
香穂はちょっと訝し気に千鶴を見た。
「そんなに大事にされている御守なら、なおさらのことです。いただけません」
公平は再度断った。
「私はいつか、このお守りを渡す人が現れるって何十年も思っていたの。それがあなた。もらってちょうだい。お願いだから」
千鶴の目が懇願していた。
「受け取ってやってください。母がこんなに自分の意志で話をするなんて初めてのことです。きっと野々村さんに差し上げたい理由があるのだと思います」
ちょっと間を置いて公平は承諾した。
「分かりました。ではいただきます。ありがとうございます。大切にします」
公平は千鶴に深く頭を下げた。千鶴は嬉しそうにそれを手渡すと安堵して言った。
「公平さん、ありがとう。あなたに会えてよかった。お母様のお導きかしらね。長い間、ここであなたを待っていたような気がするの。何故かしら。でも、胸につかえていたものがとれたわ」
ホッとした千鶴の笑顔は穏やかだった。
「僕こそ、お会いできてよかったです。いいお話をお聞かせいただいてありがとうございました」
公平は名残惜しかった。千鶴は優しい笑顔で頷いた。
「香穂さん、お腹が空きました」
「はいはい、帰りましょう。帰ってお味噌汁作りますね。おかあさんに習ったお味噌汁」
香穂も嬉しそうに千鶴の手をとった。そして千鶴を支えながら静かに歩き始めた。
「ちぃ先生、またきっとお会いしましょう。お元気でぇー」
公平は二人の背中に呼びかけた。二人は同時に振り返ると笑顔で頷いた。それは本当に優しい表情だった。
それにしても、何故、俺になんだろうか? 公平はその御守を腰につけたジョギングポーチにしまうと、そう思いながらまた走り始めた。
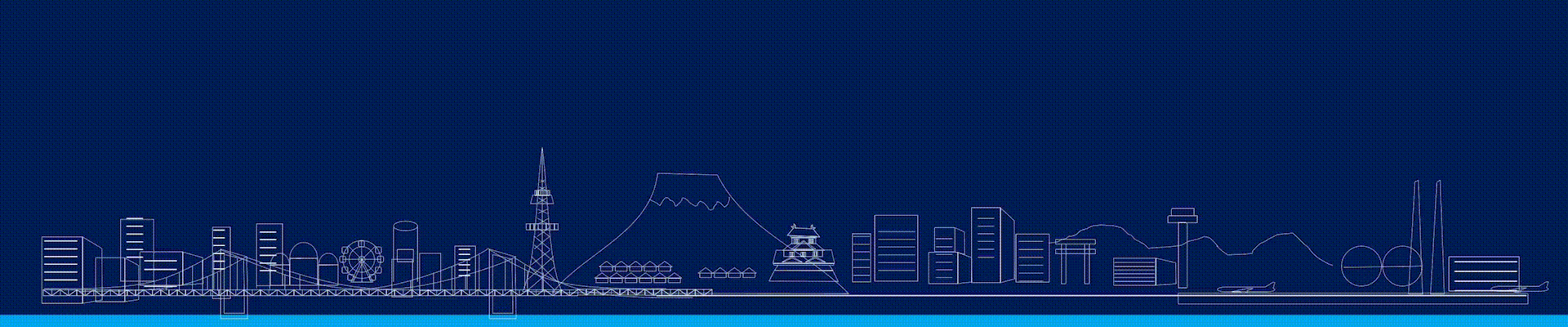





Login to comment
サインイン