確信の出発ち1
「おはようございます」
公平はすれ違う人に声をかけた。毎朝、野川をジョギングやウォーキングをする人はよく見かける顔が多い。自然とお互いに顔だけは知ることになり朝の挨拶を交わすようになる。
公平は数人の人たちが望遠レンズをつけたカメラを三脚に取り付け、川に向けている様子を見つけた。おはようございます、と公平が声をかけると、一人の青年が「しーっ」と口元に人差し指を立てた。足を止めた公平は思わず小声になり、「何かいるんですか?」と聞いた。
「カワセミ」と教えてくれた。
野川は何種類もの野鳥が羽を休めにやってくる。番いのマガモやカルガモの親子、首の長いアオサギ、胸が真っ白なコチドリ、そして美しい色合いのカワセミなど、その数は三十種類以上にも及ぶ。
「カワセミがいるんですか?」と公平には見つけることができず尋ねた。
「さっき、見かけたからもう一度あそこに戻ってくると思うんだよね」とその青年が指差す方向には浅瀬の中ほどにちょっと大きめの岩があった。カワセミはよくその岩に止まるという。公平よりも少し年上に見えるその青年は、なにやら鞄の中をゴソゴソと探しているようだった。
「これ見ます?」と青年は鞄の中から写真ホルダーを取り出して公平に差し出した。
「えっ? あぁ、ありがとうございます」
公平はいきなりのことで戸惑ったが、その写真ホルダーを手にした。ホルダーには美しいカワセミの写真が何枚もあった。岩の上で止まっているもの、飛び立つ瞬間の羽ばたく姿、水辺に生える小さな木の枝で首をかしげているものなど、どれも素晴らしい写真だった。
「すごいですね、この写真。全部ご自分で撮られたんですか?」
「うん、そう。土日しか来られないけど、ここはお気に入りの場所なんです」
「ご近所なんですか?」
「いや、所沢から」
「えーっ! 所沢から来たんですか? こんな朝早く」
「はい。バイクで。写真好きな人間は俺に限らず、いい場所があると、どこでも行くんじゃないかな。一応これでもフリーのカメラマンなんです。売れてないけど」
青年は照れ笑いをしながら言った。
「僕は写真のことはよく分かりませんが、このカワセミの写真は美しいと思います」
「ははは、ありがとう。でもこんなもんじゃないんですよ。凄腕のカメラマンは。ただ単に写真を撮るだけじゃなく、彼らは命をかけてシャッターを切るんです。その写真を見ると動いている錯覚にとらわれるくらい躍動感があるんです。俺の写真なんてまだまだ、せいぜい広告チラシに使ってもらえる程度。でも、いつかは俺も人を驚かせる写真を撮ってみせるっていう気持ちだけはあるんですけど。藤堂さんの写真みたいに」
青年は自分の写真家としての定義付けをしているように話した。
「藤堂さん? すごいんですか、その人」
「藤堂保弘、すごいなんてもんじゃない、あの人の作品を見ていると、その場面の音や匂いや風を感じるんです……」
青年のその崇拝する表情に公平は興味を持った。
「あなただってできますよ。だってすごいもの、この写真。このカワセミは羽ばたいているのが本当によく分かりますよ」
公平はその青年もすごい写真家になれると素直に思った。
「何だか無心でシャッター押した感じですよね」と公平はまた分かったようなことを口にしてしまった。
「無心?……そうか、無心か。そうだよな。俺は何をやってるんだ。どうして気が付かなかったんだろう。無心に戻ろう。結果は後からついてくるんだ。ありがとうございます」
青年は何かを発見し、そして反省するかのように呟くと公平の手を握った。そして大きく深呼吸をした時だった。
「来た!」
青年が小さく叫んだ。
数人が一斉にシャッターを切った。公平も息を飲んで見つめた。青緑の羽をときどき震わせながらカワセミが岩の上に止まった。三十秒も止まっていたであろうか、カワセミは再び川面へ飛び立った。
「よし!」青年が拳を握った。
「撮れましたか?」
公平もドキドキしながら尋ねた。
「うん」
青年は力強く頷き、今撮った写真の再生を見た。
隣で同じような望遠カメラを構えていた初老の紳士が残念そうに言った。
「タイミングが合ってない。あー、どれもだめだな。深田さん、うまくいった? よかったね。ちょっと見せてよ」
青年は再生モニターを見せた。
「いいねー、連続して躍動感出ているね。こりゃいい写真だ」
公平も見せてもらった。そこには止まったカワセミが飛び立つ瞬間が連写されていた。羽ばたいた翼が前方に動いた瞬間の写真だった。写真のことが分からない公平にもそのすごさを感じることができた。
「深田さん、とおっしゃるのですか? 今、お隣の方がそうお呼びになったので」公平が尋ねた。
「はい。深田と言います。あなたのお陰です」
「えっ? 俺のお陰?」
青年の言葉を理解できない公平であったが、それよりもその撮影する真剣な姿に感動していた。
「僕は野々村と言います。いいものを見せていただきありがとうございました。素人が分かった風なことを言うと怒られるかもしれませんが、きっと深田さんの写真は今に有名になりますよ。写真が何か言っているような感じがします。何かすごいものを感じるんです。深田さんの写真が何かに載るようなことがあったら教えてくださいね」
公平には初めての経験だった。そして深田の写真を見て素直に応援したくなった。
いいものを見ることができたと虎狛橋の上からいつものように母に手を合わせた。その時、優しい風が川面から公平の身体を吹き抜けた。それはあの時と同じ、菊池千鶴と出会ったあの日を思い出した。
「深田ちゃん、この鳥、なかなかいいじゃない。どこで撮ったのよ? 使わせてもらうよ」
副編集長の木村はろくに見もせず、机の上に積み上がった書類の上に投げるようにその写真を置き、適当に褒めると伝票に10,000と書き押印して深田幸樹に渡した。
「帰りに経理に寄って支払ってもらって。」
「木村さん、これ、何に使ってもらえるのですか?」
深田はいつになく今回の写真には執着した。
「うーん、まだ決めてないけど、グラフで鳥シリーズ的な? そんな企画があれば入れとくわ。」
「だったら、結構です。返してください」
「深田ちゃん、何よぉ、拗ねてんの? いい写真だからそのうち使うって」
「そんな誰の写真か分からない使い方されたくないんです」
深田はもっとよく見てほしいとの思いからつい口調が荒くなった。
木村の表情が曇った。そして今までとは違う低い声で言った。
「何様? 藤堂さんの顔もあるから面倒みてやってるのにさ、勘違いすんじゃねーぞ。こんな写真じゃ食いつけねーって言ってんだよ。藤堂さんからよろしくって言われてるから一万円だって小遣いのつもりで出してやってるのに、本気で写真で食っていくつもりなら、すごいもの持って来いよ!」
木村は伝票を奪い取ると深田の目の前で破り捨てた。
「失礼します」
深田は軽く頭を下げると渡した写真を手にしてその場を去った。外に出た深田は振り返り、今出てきたビルを見上げ、ビルの壁に縦に取り付けられた「東京旬版社」の袖看板を見つめた。写真の本当のよさも理解できないくせに。今に見ていろ。撮ってやるよ。驚く写真を撮ってやる。深田は悔しそうに呟いた。だが、一方で自分をこの会社に推薦してくれた藤堂の顔が浮かんだ。
会社からの帰宅途中、公平は書店にいた。グラフ誌や写真集コーナーの棚を目で追った。今まで写真集など手にすることなどなかった公平だが、改めてその種類の多さに驚いた。藤堂保弘、藤堂、藤堂……公平は棚に並ぶ何十冊もの写真集を指で追いながら探した。
『驚異の大自然×藤堂保弘の世界』『藤堂保弘が見る日本の美』『匠 職人の心 藤堂保弘』
あった。藤堂保弘、何冊も出てるんだな。驚異の大自然か。公平はそれを手にした。そこには信じられないような自然の写真があった。単なる壮大な風景ではなく、自然が作りだす一瞬の出来事を捉えた、まさに自然のいたずらが為す瞬間を撮ったものだった。公平はページをめくるたびに、食い入るように見た。続いて公平は、職人が働く姿を撮影した写真集を手にした。職人が左手に日本人形の頭を持ち、細い筆で目を描いている様子の写真だった。公平は深田の言葉を思い出した。あの人の作品には音や匂いや風を感じると。その写真に写っている職人の手が繊細に動いているように見えた。匠の技を感じるに十分な一枚だった。呼吸を忘れた公平は止めていた息を一気に吐いた。
「すごい。確かに写真は奥が深いな」
公平は大自然の写真集を再び手にしてレジに向かった。
「これ、ください」
「はい、ありがとうございます。7020円になります」
「えーっ! 高ぁ」
公平は値段を見ていなかった。
その週の土曜の朝、公平は深田が来ていることを期待しながらいつもの川沿いを走っていた。先週出会った人たちが同じ場所でカメラをセットしていた。公平は深田の姿を探した。
「おはようございます。カワセミ、来てますか?」
「今日はまだだよ」前回撮影に失敗した紳士が言った。
「そうですか、今日は、深田さんは?」
「今日は姿見てないね。そう言えばこの間の深田さんの写真、よかったよね、売り込みに行ったかな」
写真仲間としては応援したいのだろう、居合わせた人たちがそれぞれにそのことを口にした。見事なまでにピントの合ったあのカワセミの写真を仲間は絶賛した。
「深田さんは我々のようなアマチュアと違って、プロだから、カワセミに対する気持ちが半端じゃない、生態を調べたりしてね、撮る姿勢が我々とは違う。成功してほしいな」
「じゃあ、先週のあの写真もどこかの雑誌に掲載されるかもしれませんね」
公平も嬉しくなった。
「あれは売れると思うな。あのシャッターを切った時の深田さん、すごい顔をしていたよな。あれが魂のシャッターなのかな」
「魂のシャッター? すごい写真を撮った時にそう言うのですか?」
「いやいや、深田さんが師事する藤堂保弘の言葉だよ」
「僕も藤堂保弘の写真集、買ったんです。すごい写真だと思いました。本当に躍動感のあるものばかりで、今まで写真なんかに……、ああ、すいません。なんかとか言っちゃって。でもあまり興味なかったんですけど、あの写真集を見て考えが一変しました」
公平は写真好きな彼らの仲間入りができたような気分になっていた。無性に藤堂という写真家に会ってみたくなった。
出版社の編集者を怒らせてしまった深田は、藤堂の顔に泥を塗ってしまったと猛省していた。藤堂の口利きでせっかく紹介してもらえた出版社だった。おこぼれの仕事でも一応は写真家としての仕事はもらえていた。贅沢は言えなかったが、しかし、あの木村の態度は許せなかった。深田は必死に写真を勉強してきた。撮る技術だけでは駄目だと藤堂から教えられた。写真は心で撮るものだと。だから被写体には自分の全神経を注いでシャッターを切らなければならない、それが魂のシャッターというものだと。
あの時、深田の気持ちは一瞬、カワセミと一緒に飛び立つ感覚でシャッターを切っていた。飛び立つカワセミの真横にいるように被写体を見た。その時、時間が止まった。羽ばたくカワセミがコマ送りに見えた。初めての感覚だった。撮り終わった時、手は震え、腰が抜けるほどの脱力感が襲ってきた。それほど集中していたのだ。
深田は藤堂に謝るために自宅を訪れた。まだまだ認められる写真家ではないと自分でも分かっていた。ただどうしても写真を軽く見るあの木村が許せなかった。
もう、あの出版社には出入りできないと覚悟した。他には出入りできる出版社はなかったが。
藤堂の住むマンションに着いた。セキュリティがしっかりしているマンションだった。一階の玄関ホールからからインターホンを押した。
「はい、どちら様ですか?」藤堂夫人の声だった。
「あ、すいません。深田です。大変ご無沙汰いたしております」
「あら、珍しい。今開けますね」
入り口のドアが開いた。深田は気が重いながらもエレベーターのボタンを押した。藤堂の部屋は八階にある。エレベーターが長く感じた。部屋のインターホンを再度押すと夫人が笑顔で迎えてくれた。
「お久しぶりね。お元気でした?」
藤堂夫人は美大で油絵を教えている品のいい女性だった。藤堂の一回り年下だったが歳の差を感じさせない夫婦だった。
「はい、ありがとうございます。なんとか生活しています。先生はご在宅ですか?」
「ちょっと、そこまで出かけていますけど、すぐに戻るから上がってお待ちになって」
夫人は深田を居間に通すと紅茶を入れてもてなした。アールグレイのいい香りが漂った。
「どうぞ、召し上がって」
「ありがとうございます。いただきます」
「最近はどうされているの? 写真の方は順調なのかしら?」
夫人は深田に、藤堂が目をかけていることを理解していた。
「なかなかうまくはいきません。でも真剣に取り組んでいます」
「そう、私は写真のことはよく分からないけど、深田さん、若いうちはなんであれ妥協しないでね」
「はい、それは藤堂先生からいつもきつく教えられています。そこが私の弱いところかもしれません」
深田はアルバイトで生計を繋いでいるが、時折依頼される広告の写真の仕事は本当に真剣にシャッターを押しているかと自問することが多く、そのたびに自己嫌悪になってしまう自分がいた。
「深田さん、ちょっといらして」
夫人はそう言うと自分のアトリエに案内した。あまり広くはないが、油絵の絵の具の匂いが立ち込めた、いかにも画家の仕事場といった感じがしだった。
「今度の展覧会に出品するつもりなの」
それは淡い水色をベースに白い筋雲を描いた二枚組の油絵だった。
「この絵、まだ名前がないの。深田さんならどんな題名をつけるかしら?」
深田は暫しじっと二枚の油絵を見つめた。
「風水の神……」と深田は答えるわけでもなく呟いた。
「ただいま」知らぬ間に藤堂がアトリエの入り口に立っていた。
「あっ、お帰りなさい、先生。ご無沙汰しております」
「あら、あなた。お帰りなさい。今、深田さんに今度出展する絵の感想をきいていたの。的確に評してくれたのよ」
夫人らしい深田への励ましだった。
「いえ、とんでもございません」
「ゆっくりしていってね」
夫人は藤堂と深田を自分のアトリエから見送りながらに笑顔を見せた。
「深田、久しぶりだな」藤堂は深田の顔をじっと見つめて、「何かあったのか? 去年のコンクール、何故出展しなかった? やってみろと言っただろ」
藤堂は深田の表情から何かを察したが、それには触れず、昨年の若手写真家コンクールの話をし始めた。
「すいませんでした。自信がなくて、まだ勉強不足です」
昨年、深田は広告代理店から依頼されて撮影したお菓子の写真に、スポンサーからイメージが違うとクレームをつけられ、仕事をキャンセルされたのだった。そのせいか出展のために撮ったカワセミの写真が急に駄作に思えてしまったのだ。
「まあいい。お前が納得できない写真を出しても意味がない」
「申し訳ありません。先生、もう一つお詫びしなければならなくて、伺いました」
「そうか、どうせ、たいしたことではないだろうが聞こう」
藤堂は深田の気持ちの弱さを治さなければ写真家としては致命的だと思っていた。それは彼がどんなにいい腕を持ち、そして大きなポテンシャルを秘めていたとしても。
「実は、先日、木村さんのところに行きまして……」
「木村?」
「東京旬版社の……」
「ああ、編集の担当者か」
「副編集長です」
「まあ、肩書きはどうでもいいが、彼がどうかしたのか?」
「はい、また写真を持ち込ませていただいたのですが、木村さんを怒らせてしまって……」深田はその時の出来事を話した。
「せっかく、先生にご紹介していただいたのに本当に申し訳ございません」
「その写真はどうした?」
藤堂は深田が木村に言った言葉が気になった。いつもの気の弱い深田なら一万円で写真を渡して帰ったはずだ。それをしなかったことが気になったのだ。
「ここにあります」
深田は黒い布製の大きな鞄を押さえるように言った。
「ちょっと見せてくれないか?」
「勘弁してください。勉強不足なのに生意気なことを言ってしまって」
深田は写真のことよりも藤堂の立場を気にしていた。
「いいから、見せてごらん」
深田はしぶしぶ鞄から写真ホルダーを取り出し、三枚の写真を抜き取り藤堂に渡した。藤堂はじっとそれを見つめて言った。
「カメラの中にまだ入っているか?」
「はい。入っています」
深田は鞄からニコンD810を取り出して渡した。藤堂はカメラを受け取ると自分の部屋に行き、しばらくして戻ってきた。
「なかなかいい出来じゃないか」
藤堂がそう口にすると深田は木村に言われた言葉が重なり思い出された。深田ちゃん、なかなかいいじゃない。深田は瞑った目を見開いて言った。
「先生、もっともっと勉強します。もっと力強い写真を撮ります。本当に申し訳ございませんでした」
そういうと深田はそそくさと藤堂宅をあとにした。
藤堂は何も言わなかったが、深田が気持ちの弱さから抜け出したことを確信した。
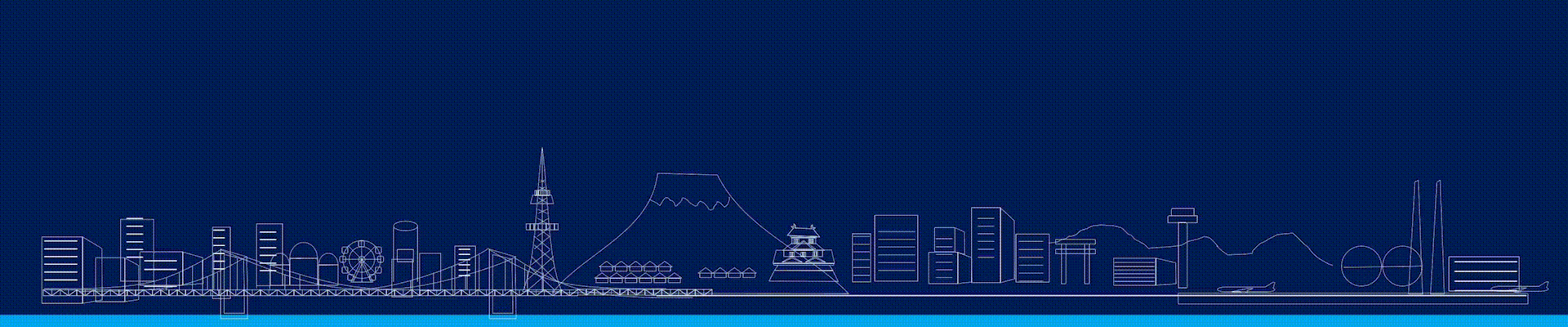






Login to comment
サインイン