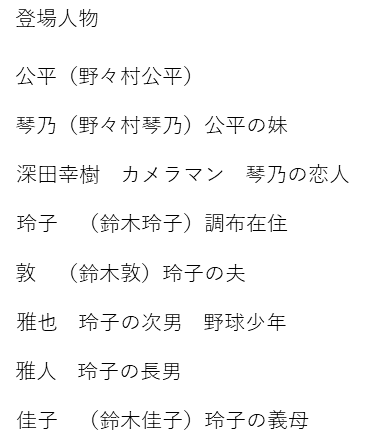
「もしもし、お母さん? 玲子です」
鈴木玲子が田舎の義母に電話をしたのは初夏のことだった。
「あら、久しぶりね。みんな元気にしているの? 雅也の具合はどう? 敦は相変わらず海外出張が多いのかしら?」
「ええ。お陰様でみんな元気にしています。雅也もときどきぜいぜいすることはあるけど前みたいなひどい発作は起きなくなりました。雅人はそろそろ大学受験に取り組んでほしいのですが、のんびりしています。今度お母さんからも言ってやってください」
「いいじゃないの。本人がその気になればやるわよ。でも雅也が元気でよかった。ちょっと安心したわ」
「お母さんは? 体調はいかがですか?」
「私は大丈夫よ。今年はトマトが美味しく実ったからまた送るわね」
「まだ畑、やっているのですか? もう年なんだから気をつけてください」
玲子は姑を気遣った。
「お父さんと一緒に畑をやっているから元気なのよ」
玲子の嫁ぎ先の義父は長年町役場に勤め、引退した後は夫婦で小さな農場を買って野菜の栽培をして暮らしていた。
「でもあんまり無理しないでくださいね。ところでね、来月、敦さんが東京本社へ転勤することになったんです」
「あら、そうなの」
玲子は夫と二人の息子とともに大阪で暮らしている。夫の敦は総合商社の大阪支社で働いていた。海外の食料品、主に加工材料の買い付けを担当していることから海外に長期で出張することが多かったが、東京本社の食料品本部との部門統合で東京に異動となったのだ。
「だから急にバタバタと引っ越しの準備をし始めたところで。今度はそっちに少し近くなりますからまた行きますね」
「もう住むところは決まったの?」
「はい、会社が社宅として借り上げているマンションが東京の調布というところにあるそうで」
「調布……」姑の声の調子がちょっと変わった。
「はい、調布。どうかしましたか?」
関西出身の玲子は東京に住んだことがなく、調布がどこなのかもよく理解していなかった。
「いいえ、どうもしないよ。そうなの、調布に住むのね」
「引っ越しの日程が決まったらまた連絡しますね」
早朝とはいえ、七月のジョギングは暑い。公平はいつものように虎狛橋の上で全身汗だくになってストレッチをしていた。土曜日の野川はこころなしか散歩をする人が多い。数日前に降った雨で水かさが増えた川面から何匹もの亀が顔を出していた。伸びた水草の間を鴨の親子が気持ちよさそうに水浴びをしている。朝から夏休みの子供たちが浅瀬で網を持って小魚を追っていた。岸からは父親らしい大人が注意を促しながらも笑顔で子供達と楽しそうに話しているのが聞こえる。公平は一度だけ父親と野川で遊んだことを覚えている。微かな父との思い出もまたこの野川にあった。
さあ、帰ってシャワー浴びてのんびりするかぁ、公平は復路を走り始めた。
川面を泳ぐ鴨を横目で見ながら公平はゆっくりとしたペースで走っていたが、その川岸で小学校高学年らしき男の子がうずくまり苦しそうにしているのを見つけた。公平は急いで土手を下りその子に近づいた。
「きみ、どうした? どこか痛いのか?」
その子はぜいぜいと息苦しそうにして言葉が出ない様子で咳き込み、息を吸うとヒューヒューと音がした。
顔色は青ざめ唇が紫色になっている。それを見て、公平はやっと思い当たった。小児喘息だ。
持っていたペットボトルの水をゆっくり飲ませると呼吸が少し落ち着いたので、ほっとしながら聞いた。
「大丈夫だよ、家まで送っていこう。住所はどこかな?」
かろうじて住所を聞くと公平はその子を背負った。道を尋ねながら急ぎ足で家まで送り届けると、中から母親らしい女性が出てきた。
「お母さんですか? 近くの川原で息苦しそうにしていたので、おぶってきました」
公平は青白い顔色の少年を下ろすと大丈夫かと肩を支えた。
「雅也! 大丈夫? すいません、ここに座らせてもらえますか?」
玄関脇の小さなスツールを示すと母親は奥の部屋に走って行き、間もなく小型の吸引機を抱えて戻ってきた。
「はい、雅也、くわえて。そうそう、ゆっくり息吸ってね。ゆっくりでいいよ」
母親は子供の背中をさすりながらしばらくその姿勢を保った。やがて雅也の顔に赤みが差してきた。そして大きく深呼吸しながら立ち上がった。
「もう大丈夫やね」母親はその顔を覗き込むようにして確かめると抱きしめた。
「うん。大丈夫」少年は平常を取り戻したようだ。
「よかった」公平も胸を撫で下ろした。
「ありがとうございました。この子は喘息でときどき発作を起こすんです。最近はずいぶんとよくなってきたのですが、引っ越しや転校なんかで疲れていたのだと思います。なるべく外の空気を吸って無理のない運動をするように言われているので、今朝も散歩に行くと言って。助けていただき本当にありがとうございました」
「いいえ。大事にならなくてよかったです。どちらから引っ越されてきたのですか?」
「はい、大阪から最近こちらに引っ越してまいりました。あのー、失礼ですがお名前を?」
「ああ、申し遅れました。野々村と言います。私もこの近所に住んでおります」
「そうですか。東京は何分初めてのことで、この子もまだ学校とこの川原くらいしか歩いてないんです。今日は助かりました」
「俺、毎日出勤前に野川をジョギングしているんだけど、今度一緒に走らないか? 無理のない程度に。雅也君は何年生?」
公平は雅也に目線を合わせて言った。
「ホンマですか?」大阪弁の雅也は嬉しそうに答えた。
「雅也! まずはお礼でしょ!」
叱られて雅也は首をすくめた。
「今日はありがとうございました。鈴木雅也です。六年生です」
「雨の日と仕事で出張ってる時以外は毎朝ジョギングしているから、体調がよければお母さんのOKをもらったら六時に虎狛橋においで」
「ご親切に本当にありがとうございます」
鈴木玲子は深々と頭を下げて礼を言った。
「では、これで失礼します」
公平は挨拶をすると雅也に喘息なんかに負けるなと笑顔で励ました。
鈴木雅也はいつも一人だった。同じマンションに住む同級生とは学校で仲良くなったが、土日になるとその同級生たちは皆朝から少年野球に出かけてしまい、近所で遊ぶ相手がいなかったのだ。雅也はユニフォーム姿でリュックにバットをさした友達が自転車で出かけるのを羨ましく見ていた。小さい頃から喘息で体育の授業は休みがちだったが、学年が上がるにつれ体力もつき始め、症状は以前よりもよくなっていた。しかし、激しい運動にはまだ自信がない雅也は、野球は自分とは別世界のことと諦めていた。そんな息子を母の玲子はなんとか強い子にしたかった。高校二年生になる雅也の兄とは少し年が離れていることもあり、過保護に育ててしまったのではないかと玲子は反省していた。
翌朝、虎狛橋に雅也が来ていた。
「野々村さん、おはようございます」雅也はニコニコと挨拶をした。
「おー、雅也君、来たか。大丈夫なのか?」
公平はまさか翌日に来るとは思っていなかったので少々驚いたが、雅也の笑顔を見て一緒にウォーキングをしてやろうと思った。
「はい。お母さんに無理をしないからと言ってOKをもらいました」
「そうか、じゃあ行くか」
公平は既に汗だくだった。雅也は、はいと答えると走り始めようしたが公平は止めた。
「最初から走っちゃだめだよ。また喘息が出るぞ。今日はウォーキングにしよう。徐々にペースを上げていけばいいよ」
公平は雅也と話しながら歩き始めた。
雑草が伸びてきた川岸で犬の散歩させていた数組の人達が朝の談笑で盛り上がっていた。
「野々村さんは運動が得意ですか?」
「まあまあかな。あのさ、その野々村さんって呼ぶのは勘弁してよ。公平さんでいいよ」
「はい。公平さん」
「雅也は大阪生まれなの?」
「そうです」
「もう慣れた? 東京の生活は」
「はい、少しだけど学校の友達もできました。でも、同じマンションの友達は、野球に行って、土日は皆おらんようになります」
「じゃあ、雅也も野球、やればいいじゃん」
「僕はあかんよ。喘息やし、身体弱いし、野球なんてでけへんよ」
「そんなの、やってみないと分からないだろ」
「でも、僕なんか入れてくれないよ」
雅也はやりたいけどそんな環境にないことを恨めしく思っていた。二人は細田橋の上でしばし足を止め、野川を泳ぐ鯉を見ながら話を続けた。
「一度練習の様子を見学に行ってみたらどうかな。お母さんに頼んでさ。やれるかもしれないじゃないか。やってみたいと思わないか? 友達と一緒に野球をさ」
「そりゃ、やりたいけど……できるかな」
「できるさ、駄目だったら、また考えればいい。何もやらないで諦めたら必ず後悔するよ」
公平は雅也の頭を撫でた。雅也はしばらく考えていたが吹っ切れたように顔を上げた。
「うん。やってみる」
雅也の心にふつふつと元気が湧いてきた。
「そうだよ、頑張ってみろよ」
公平が雅也を励ました時、川面から風が吹き上げてきた。風は二人の身体の中に暖かさを残して吹き抜けていった。あっ、またあの風だ。
多摩川の河川敷にある少年野球のグラウンドは、多くの小学生選手の元気な声が飛び交い、いくつものチームが練習をしていた。少年野球チームは小学校の学区により入団する学童を分けていた。玲子は予め同じマンションにいるチームの父兄にどのチームに行けばよいかを聞いていた。公平から野球を勧められたことを雅也から聞き、玲子も思い切ってチームのドアを叩いてみようと雅也とともにグラウンドにやってきたのだった。チームはちょうど練習が始まったばかりで、大きな声を出し合いながらキャッチボールをしていた。玲子はグラウンドの端で選手たちの給水用のジャグを用意している父兄らしき女性に声をかけた。
「すいません。調布マリンズの方ですか?」
「はい。そうです」
「練習の見学をさせていただきたいのですが、どなたに言えばよろしいでしょうか?」
「ああ、見学ですね。歓迎ですよ。ちょっと待ってくださいね」
そう言うと女性は一塁側ベンチに座っていたユニフォーム姿の監督らしき人のところに行き一言二言話をした。すると、その人はすぐに立ち上がり玲子と雅也に近寄ってきた。
「こんにちは。監督の山村と言います。見学ですか?」
「最近こちらの方に引っ越してきました鈴木と申します。よろしくお願いします」
「君は何年生?」山村は雅也に直接聞いた。
「六年生です」
「そうか、じゃあ、このチームだ。野球はしたことあるか?」
山村はにこやかに聞いた。少年野球は基本的に学年ごとにチームが編成されており、山村は六年生チームの監督だった。
「前の学校でソフトボールはしたことがあります」
雅也は野球経験がないことで入れてもらえないのかと不安な顔になった。
「おー、そうか。だったら大丈夫だな」
山村は安心させるように笑顔で話した。
「あのー、実はウチの息子は喘息があるのですが、そうした子供はチームには入れていただけないでしょうか?」
玲子はおずおずと尋ねた。
「大丈夫ですよ。お預かりします。無理のない範囲でやるようにします。お当番のお母さんたちが必ずグラウンドにはいますから、何かあればすぐに対処できます。喘息はひどいのですか?」
「最近は小さい頃よりは発作も少なくなり、通常の生活は問題ないのですが、一度発作が出るとしばらくぜいぜいとしてしまいます。他の皆さんにご迷惑がかかるかもしれません」
「運動をすることに問題はあるのですか?」
「お医者様からは、なるべく外の空気を吸って運動もするように言われています」
「そうですか。だったらいいじゃないですか。野球を楽しむことが一番ですから。まあ、今日一日体験して本人がやれそうなら入団させてみてはいかがですか?」山村は前向きに入団を勧めた。
「ありがとうございます。近所の友達が皆、土日は野球に行くのを見て本人もやりたい気持ちはあるのですが、どうしても喘息があることで自信がなかったようなのです。でも最近になって、やっぱりやってみたいと言い出しまして」
山村は雅也の目線に合わせて屈んで言った。
「鈴木君、下の名前は?」
「雅也です」
「よし、雅也、グローブは持っているか?」
「持っていません」
「大丈夫。青柳さん、余っているグローブ持ってきていましたっけ?」
山村は先ほどの女性に声をかけた。
「はい。いくつかあります」
「じゃあ、自分で好きなのを選んでおいで」
「はい」
雅也はワクワクし始めた。青柳加奈子はキャプテンの母親で、雅也に程度のいいグローブをいくつか渡した。
「どれでもいいよ。これは卒団した人が寄付してくれたものだから遠慮は要らないのよ」
「ありがとうございます。じゃあ、これ、いいですか?」
雅也は一番使い込んだものを選んだ。
「それでいいの? もっと新しい方がいいんじゃない?」
加奈子は別のものを勧めたが、雅也はその使い込んだグローブが気に入った。
「集合―!」
山村が大声でキャッチボールをしている選手たちに呼びかけた。全員が全速力で駆け戻り監督の前に集まった。
「今日、体験練習に参加する鈴木雅也君だ」
「おー、鈴木」
声をかけたのは同じマンションの須藤亮介だった。雅也ははにかんだように亮介を見た。他にも学校の友達が数人いたが、知らない顔が多かった。このチームには三つの小学校の学童が入っている。
「よろしくお願いします」
雅也は少し照れたように挨拶をした。
雅也が練習をしている間、玲子は青柳加奈子からチーム運営に関していろいろと説明を受けた。玲子は加奈子に他の子供たちの足手纏いにならないかと心配していることを正直に話した。
「少年野球は学童の健康と健全な心の育成の場というのが前提だからね。監督も他のコーチも考えてレベルに即して指導してくれると思うわよ。ウチの子がキャプテンだから私からもウチの子には言っておくわ」
加奈子は玲子よりも年下のようだが、しっかりとした説明に玲子は頼りがいを感じた。
「ありがとうございます。よろしくお願いします」
玲子は温かく迎えてくれるチームに安堵した。
そして、この日、雅也は喘息の発作が出ることもなく練習を終えることができた。監督の指示の下に練習後のグラウンド整備を皆で行い、グラウンドに向かって整列をし、無事に練習が終えられたことに感謝する、それがチームの決まり事であった。キャプテンの号令で一斉に頭を下げる。
「ありがとうございました」
「雅也、どうだった? 一緒に野球をやらないか?」
山村が聞いた。すると亮介が「一緒にやろうぜ!」と声をかけてくれた。他の子供たちも「入れ、入れ、入れ、入れ……」と声を揃えた。雅也は嬉しかった。
雅也の背番号は14に決まった。入団後、雅也は一生懸命に練習に励んだ。とにかく、友達と同じユニフォームを着て多摩川のグラウンドに来るだけで楽しかった。他の子供たちも雅也の喘息は承知していたので、それなりに親切に接した。そうかと言って、山村が特別扱いをすることはなかった。体調の変化には気をつけながらも他の子供たちと同じように指導した。雅也にとっても、自分も他の選手と同じように扱われることが嬉しかった。雅也は自分が他の選手に比べ技術的に劣っていることは分かっていたので、自分のできる練習に努力を重ねた。ときどき苦しくなると、お尻のポケットに入れた携帯の呼吸用マウスピースを口にしながら頑張った。やがて、雅也の動きも野球らしくなっていった。
八月、秋の大会に向けてチームは毎年恒例の夏合宿を行った。盆休みに合わせ二泊三日の合宿だった。玲子は合宿先での子供たちの世話をする随行父兄を買って出た。雅也がもし喘息の発作を起こした時に他に迷惑をかけないようにという思いがあったからだ。玲子も雅也が日に日に元気になっていく様子を実感していた。
合宿所の民宿には雅也の父の敦から差し入れが届けられた。敦の会社がヨーロッパのメーカーに卸しているカカオを使ったチョコレートだった。
雅也が世話になっている礼と共に練習後の疲れに甘い物を補給してくださいと監督宛にメモが入っていた。日頃忙しく雅也の野球を応援に行けない代わりに、せめて自分のできる応援をしたいとの気持ちからだった。子供たちは外国のチョコレートを大喜びで分け合った。雅也は父親からの贈り物をチームの仲間が喜んでくれるのが嬉しかった。
見たこともないチョコレートの箱にはバレンスタインと書かれていた。
秋季大会が始まった。調布マリンズは順調に勝ち上がり、準決勝は五対〇で相手を破ると決勝に駒を進めた。決勝戦の朝、いつもと違い雅也はユニフォームを着て早くから琥珀橋に立っていた。公平が来るのを待っていたのだ。公平とジョギングを始めてから、雅也はほぼ毎日早朝のジョギングを続けていた。早朝の空気は雅也の喘息には合っていたのか、無理のないジョギングは雅也の喘息を間違いなく快復の方向に向かわせていた。
「公平さん」
「おう、おはよう。雅也、かっこいいな、ユニフォーム姿」
公平は初めて雅也のユニフォーム姿にたくましさを感じた。
「公平さん、今日な、決勝戦なんや。僕は出えへんけど応援に来てくれへんかな」
雅也は小学生最後の大会を公平と一緒に見たかった。
「そうか、決勝戦か、ヨォし行くぞ。雅也だって出るチャンスあるかもしれないからな」
「それはないと思うけど、皆と一緒に野球できるようにしてくれたんは公平さんのお陰やから、最後の試合を見てほしいねん」
雅也は嬉しそうに走り出した。
雅也は入団してから一度も公式戦に出場したことはなかった。本人もレギュラーメンバーとは実力の差は理解していた。それでも仲間と一緒のグラウンドにいることで十分に満足していた。いつも試合が始まるとベンチから大声で応援をしてきた。仲間が打つと自分のことのように歓喜し、負けると悔し涙を流した。この秋の大会が終わると六年生は引退する。優勝して都大会の出場権を取ればもう少し仲間と野球ができる。そう思うと今日の決勝戦はいつも以上に応援する気持ちが強くなっていた。
しかし、雅也は他の選手に勝るとも劣らない選球眼を持っていた。集中してボールの中心を打つ練習を積み重ねてきたことを山村は知っていた。
― 秋晴れの多摩川河川敷 ―
午後の決勝戦に向けて両チームは丹念に練習を行っていた。雅也も一球一球、確認するようにバッティング練習をしていた。確実に芯に当てるように集中する姿を山村は見ていた。
「雅也」
休憩時間で腰を下ろしていた雅也の背後から声がした。
「おばあちゃん! いつ来たん? おじいちゃんも一緒?」
「午前中に来たのよ。おじいちゃんは畑で腰を痛めたから残念だけど来られなかったの。たいしたことないから心配はいらないよ。おじいちゃんは来られないけど秩父から応援してるって」
祖母が雅也の野球姿を見たくて田舎から出てきてくれたのだった。
「応援してるからね。頑張ってね」
「でも、おばあちゃん、ごめん、僕はレギュラーやないから試合には出えへんのよ」
「いいよ、応援だって大事なことだよ。頑張って。一緒に応援するから」
「うん。ありがとう」
「おばあちゃんに雅也が元気になったって電話したらね、おばあちゃんが雅也に会いたいって言ってね。だから雅也に内緒で驚かせようと思って連れてきたの」
玲子も元気になった雅也を義母に見てもらいたかった。雅也も嬉しそうに頷いた。
「雅也、来たぞ」
公平が琴乃と深田を連れて現れた。その後、琴乃は深田と順調な付き合いを続けていた。この日も琴乃に誘われ深田はカメラを手にしてやってきた。
「あっ、公平さん」雅也の声で玲子も振り向いた。
「ああ、野々村さん、その節はありがとうございました。その後も毎朝一緒に走っていただいて、お陰様で見違えるように元気になってきました」
玲子は雅也の喘息を助けてもらってから公平には会っていなかった。
「とんでもございません。雅也君が元気になってよかったです」
「野々村さんのお陰です」
「いいえ、雅也君の頑張りですよ」
「ことのせんせーい」
ちょっと離れたところから可愛らしい声が聞こえた。見るとだぶだぶのユニフォームを着た一年生から三年生の低学年チームの子供たちが応援に来たところだった。その中に琴乃の保育園を卒園した教え子が手を振っていた。
「あらー、海斗君。一年生になって野球やってたんだ。かっこいい!」
琴乃の言葉にどや顔になる教え子がおかしくも愛おしかった。
深田は試合前の様子をいろいろな角度からシャッターを切っていた。
そして、試合が始まった。
準決勝まで好調だったマリンズの打線は沈黙していた。相手のピッチャーからクリーンヒットを放つことができない。四球と内野安打、それに相手のエラーで一点を得たものの、あとに繋げない状態が続いた。打線は完全に相手が上回っていた。一対一で迎えた最終回裏の攻撃、山村は相手の勢いから延長戦になれば負けると予感した。なんとしてもこの回で決めたかった。先頭打者がボールをよく見て四球で出塁した。しかし、その後が続かない。ランナー一塁のままツーアウト、次の打者は三番、須藤亮介だった。当然三番打者に期待するところだったが、この日、亮介は全打席三振をしていた。本人も打てない焦りから軸足が定まっていなかった。山村はタイムをかけ亮介を呼んだ。
「亮介、雅也に打たせようと思う。いいか?」
山村は亮介のプライドも考慮して本人の意見を求めた。
「えっ?」亮介は一瞬なんでという顔をしたが、すぐに笑顔になって言った。
「うん、いいよ。あいつ今日の練習でいいバッティングしてたからな」
「よし、じゃあベンチで応援頼む」
山村は亮介にベンチをまとめるように指示してから審判に告げた。
「代打、鈴木」
ベンチも応援に来ている父兄も一瞬どよめいた。
「雅也! 代打だ。行ってこい」
「えぇ! 僕?」
「そうだよ、お前だよ。他に鈴木雅也はいるか!」
山村が気合を入れた。玲子はそれを聞き、あまりの驚きに一瞬、気が遠のいた。
初めての公式戦、雅也は緊張した。心の準備はまったくできていなかった。まさか、こんな場面で自分がバッターボックスに立つことになるとは思いもしなかった。それは応援するチームの誰もが予想しなかったことだった。
「ムリ、僕じゃ打てないよ」
雅也は緊張よりも恐怖を感じていた。
「大丈夫だ! 思い切っていってこい」
山村が雅也のお尻を叩いた。
周囲で応援していた父兄たちからも声がかかった。
「雅也、頑張れー」
「雅也―! 思い切って振ってこい。雅也ならできるぞぉ」
公平も大声を出した。
ベンチの他の選手たちが立ち上がり、それぞれに声を出し始めた。
「いよいよ俺らの秘密兵器の登場だー!」
キャプテンの青柳義彦が相手のピッチャーに聞こえるように言った。
「行っけー行け、行け、雅也」
亮介が音頭を取って声を出した。全員が続いた。
「行っけー行け、行け、雅也」
「打ってー打て、打て、雅也」
「打ってー打て、打て、雅也」
全員が声を揃えてのエールだった。
その応援に雅也は背中を押された。玲子も祖母も手を合わせた。雅也がバッターボックスに入った。
「雅也、一発頼むぞ!」
「思いっきりいってこいよ」
ベンチの全員が声をかけた。
それでも初めてのことに雅也の緊張はベンチから見ていても手に取るように分かった。全身に力が入りすぎてバットが振れない。あっと言う間にツーストライクを取られてしまった。あと一球ストライクを取られれば延長戦に突入する。山村が立ち上がった。
「タイム!」山村は雅也を呼び耳元で言った。
「何をビビッてんだよ。今朝の練習でボールの真ん中を狙って打ってただろ。同じことをやればいいんだ。お前はボールをしっかり見れるじゃないか。朝の練習を思い出せ。ボールの中心を意識しろ。どうせなら思い切り振って三振してこい。ウンコ食ったような顔してんじゃねーぞ」
「監督、食べたことあるの?」
「あるわきゃねーだろ。そんなの」
山村が笑った。さっきまで青ざめていた雅也が笑顔になった。
「いくぞー!」
バッターボックスに戻った雅也が吼えた。緊張感はなくなっていた。
ピッチャーの投げたボールがど真ん中に見えた次の瞬間。雅也は渾身の力で振り抜いた。バットはボールの芯を食った。打球はレフトの守備の横を抜く見事なヒットになった。
「やったー!」
大歓声が上がった。一塁ランナーはホームめがけて全力疾走でベースを回った。勝った。誰もがそう思った時、一塁に向かって走ったはずの雅也が一塁の手前五メートルあたりで咳き込み始めた。緊張と最大の力を出したことが喘息の発作を引き起こしたのだ。山村がベンチを飛び出した。しかし、雅也は左手を口に当て、右手を山村の方向に伸ばし、指をいっぱいに広げ山村を制止した。咳き込みながら「大丈夫」と。その情況を見た相手チームの監督が叫んだ。
「ファーストだ! ファーストに投げろ!」
負けたと思ったレフトの守備はボールに追いついてもしばし呆然としていた。監督のその声にはっとしたレフトがファーストめがけて投げた。
そこにいた全員が、まるでスローモーションを見ているようにボールの行方を追った。レフトから戻ってくるボールと必死に一塁に向かって走ろうと足を運ぶ雅也の姿をそこにいた両チームの全員が息を飲んで見つめた。雅也が一塁に倒れこむように手を伸ばした。雅也の手がベースに着くのと一塁手の捕球は同時に見えた。一瞬の静けさがあった。
「セーフ! セーフ!」
審判は大きなジェスチャーでジャッジした。勝った。大歓声があがり、ベンチから選手が全員、一塁に駆け寄った。
「雅也!やったな!」
「雅也、すげーぞ!」
「雅也ありがとう!」
歓喜の言葉にもみくちゃにされながら雅也は照れながらも最高の笑顔で何度も「うん、うん」と頷いた。両チームから大きな拍手が起こった。両チームのお母さん応援団が雅也の頑張りに泣いた。玲子も祖母も顔を覆った。
「ありがとうございました。私も野球少年の母の仲間入りができた気がします」
玲子は山村とチームの人たちに頭を下げた。
「これ見て」
深田幸樹が琴乃にカメラのモニターを見せた。それは雅也がベースにタッチした瞬間を捉えている。その画像は、雅也がセーフであったことをはっきりと証明していた。
「お兄ちゃん、保育園の智子先生から電話があって、園長先生のお母様が救急で病院に運ばれたっていうから、先に帰るね。ちょっと病院に行ってくる」
「そうか、気をつけてな。深田さんは?」
「幸樹さんは夕方からスタジオの仕事があるからって先に行ったわ」
そう言うと琴乃は先にグラウンドを後にした。
「野々村さん、今日はありがとうございました」
玲子が声をかけた。
「すごい試合でしたね。こんなに感動した野球を見たことがありません。雅也君、かっこよかったなー」
公平も感動をそのまま伝えた。玲子は我が子を世界中に自慢したかった。
「野々村さん、母です」
玲子は隣にいる雅也の祖母鈴木佳子を公平に紹介した。
「ああ、雅也君のお祖母さんですか。雅也君すごかったですね。あとで褒めてやってくださいね。お祖母さんの応援があのヒットを打たせたのかもしれませんね」
鈴木佳子は公平を見て一瞬、亡くなった兄を思い出してはっとした。公平が若い頃の兄に面影が似ていたのだ。
「どうかされました?」公平が聞いた。
「いえいえ、何でもございません。皆様のお陰です。本当にありがとうございました。田舎から出てきてよかったです。こんな孫の姿を見ることができるなんて幸せです」
「そうですか、どちらからお越しになられたのですか?」
「はい、秩父からです」
「ええっ!秩父ですかぁ!」公平は美紗子の故郷と同じことに親しみを込めて復誦した。
「秩父には何か思い出でもおありですか?」佳子は公平の言い方に何かを感じて尋ねた。
「私の婚約者が秩父の出身なのものですからちょっと親近感が出ちゃいました。ははは……」
「そうでしたの。野々村さんのお相手ならさぞかし素敵な方なんでしょうね。じゃあ、近々ご結婚されるのですか?」
「いやいや、気の強い女なんです。婚約してから私を置いてヨーロッパに行っちゃうような奴でして」
「あら、それはお寂しいですね」佳子が気の毒そうに言った。
「もう慣れました。あと半年もすれば帰ってくる予定なのですが」
公平はそう言いながらまだ半年もあるのかと改めて心の中で呟いた。
「ヨーロッパにはお仕事ですか? うちの主人も今はヨーロッパに行っているんですよ」
「はい。仕事で一年間、お菓子を作りに行っています」
「お菓子?」玲子はちょっと不思議そうな顔になって尋ねた。
「そうなんです。洋菓子メーカーに勤めているのですが、ベルギーの会社と提携することになって、その関係で」
「あら、うちの主人もチョコレートの仕事でベルギーに行っているんですよ。ご縁があるのかしら」
玲子はますます公平が身近に感じた。
「お祖母さんはちょくちょく東京にはいらっしゃるのですか?」
「いいえ、何年か前に老人会の旅行ではとバスに乗ったことがあるくらいです。調布には六十数年ぶりに来ました」
「えっ? お母さん調布にいらしたことがあるんですか?」
玲子も知らないことだった。
「戦時中の話です。実は私は調布町の出身なんです。当時はまだ町でした」
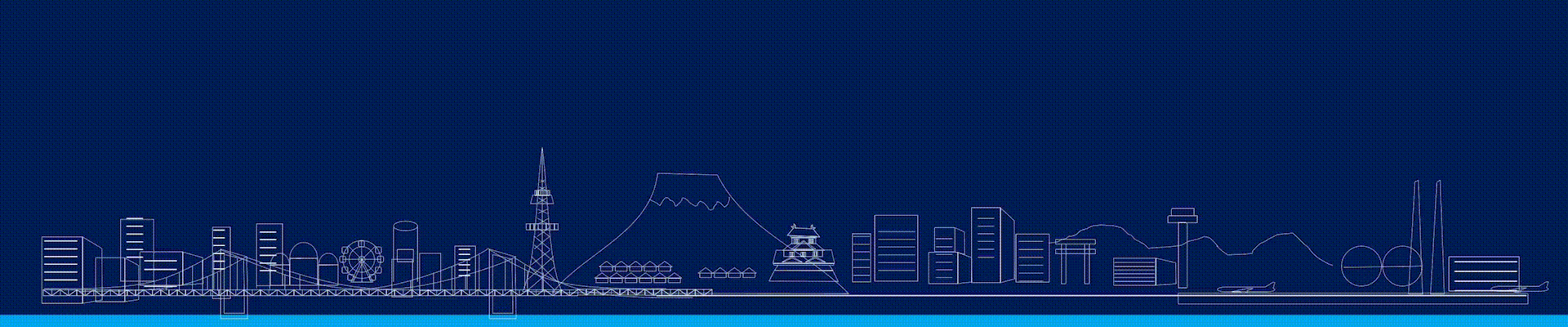







Login to comment
サインイン