連なる不思議 2
― 調慈会病院 ―
菊池千鶴は米寿を病室で迎えていた。
公平との出会いで認知症の症状は消えていたが、初夏に肝機能が低下し入院していた。
香穂は献身的に千鶴の世話をした。香穂は孤児だった。苦労して看護学校を卒業すると調慈会病院で看護師となって働いた。結婚して看護師は辞めたが調慈会病院には思い入れが強かった。当時の看護婦仲間の一人が調慈会病院の婦長になっていたことから千鶴の入院先は調慈会病院と決めていた。
千鶴の長男である夫の正則は三十八歳の時に東京都議会議員に初当選、以後七期目を迎えていた。正則が都議会議員となる前、サラリーマンだった頃に盲腸で手術をした時の担当看護師が香穂だった。正則が香穂との結婚を千鶴に告げた時、千鶴は香穂の境遇を知ると温かく菊池家に迎え入れた。両親がいないことの苦労と辛さを千鶴は痛いほどに知っていたからだった。
「お母さん、お誕生日おめでとうございます。米寿ですね。これからも長生きしてくださいよ」
香穂は千鶴の背中を摩りながら千鶴の体調を気遣った。
「香穂さん、ありがとう。あなたのお陰で幸せな最期を迎えられるわ」
「何を言っているんですか。まだまだ元気でいてくださらなきゃあ」
香穂はちょっと叱るように答えた。
「そうね、ごめんなさい。頑張らないといけないわね」
千鶴は励ましてくれる香穂に心配をかけてはいけないと思いながらも自分の寿命がもうそれほど長くはないことを感じていた。
病室は比較的大きな二人部屋で千鶴が入院した時、もう一つのベッドは空いていたが、この日、新たな患者が入院してきた。付き添ってきた家族らしい女性が香穂の様子を窺いながら挨拶をした。
「こんにちは。今日から母がお世話になります」
その女性はその患者の娘のようであった。
「こちらこそ。うちも母が入院しております」
香穂も簡単に挨拶を返した。
しばらくして、二人の女性が見舞いに入ってきた。カーテン越しにそれは若い女性だと香穂は思った。
「園長先生」その一人が声をかけた。
「ああ、琴乃先生、来てくれたの。ありがとうね」
付き添いの女性は園長先生と呼ばれた。入院したのは琴乃が勤める保育園の園長の母親だった。
「いかがですか? 大変でしたね」
そう声をかけたのは琴乃と一緒に見舞いに訪れた副園長の上山智子だった。智子は園長の土方光恵の姪だった。
「智ちゃん、迷惑かけてごめんね。午前中はなんでもなかったのよ。お昼ごはんもちゃんと食べて元気にしていたのに、居間でテレビを見ている時に急に胸が苦しいって言い出してね。さっき心電図をとったけど、今日は日曜日だから、他の検査は明日になるそうなの。狭心症の疑いがあるってお医者様から言われてね。点滴で今は落ち着いたのかしら、眠っちゃったわ。心配かけてごめんね。休みなのにわざわざ来てもらっちゃって。そんなんで、明日も検査とか担当のお医者様と話とかがあるから、保育園の方、お願いね」
「保育園の方は大丈夫ですから、こちらを優先してください」
「頼むわね。琴乃先生も協力してあげてね」
「はい。承知しました」琴乃も快く引き受けた。
三人は見舞いの人と入院患者が談話するラウンジで、保育園の秋の運動会について話し始めた。ゼロ歳児から五歳児まで百人を擁する『まこと保育園』はこの辺りでは比較的大きな保育園だった。それだけに遠足や運動会の企画は保育士にとって大変な仕事の一つだった。琴乃は主に四歳児五歳児を担当していた。保育士たちは常に横の繋がりを大切に、協力して保育に努めていた。
「運動会の集合写真を毎年お願いしていた駅前の写真屋さんが店を閉めるそうです」
智子が報告するように光恵に伝えた。
「あら、どうして?」
「後を継ぐ人がいないそうで、ご主人も健康面からもう引退することにしたそうです」
智子は調べたことを説明した。
「そうなの、じゃあどうしようか? この間は商店街の文房具屋さんも閉店しちゃったし、寂しくなってきたね」
光恵は気心知れた出入り業者が減っていくことに不便なことよりも時代の移り変わりが寂しかった。
「新しい写真屋さん、私に任せてください」
琴乃は幸樹を担ぎ出そうと考えた。
「心当たりあるの?」智子が聞いた。
「はい。実は私の彼がカメラマンなんです」
「えーっ! 彼氏がいたの!」
光恵と智子が同時に声を揃えて驚いた。
「なんでそんなに驚くんですか?」
琴乃は口を尖らせながら二人を睨みつけた。
「ごめん、ごめん。琴乃先生はいつまでも可愛らしくて、つい、うぶな感じがして仕方がなかったから。でも、そうよね。琴乃先生もそういう年頃よね」
幼く見える琴乃はいつもどこか子供扱いされがちだった。光恵が言い訳をしながらも目を細めた。光恵は琴乃が保育園に入った時から目にかけてきた保育士だったから、琴乃がちょっと大人になったように見えて、それが嬉しかった。
「じゃあ、お願いしようかしら。彼氏に」光恵は琴乃に託した。
「はい。承知しました」
「ではそろそろ帰ります」
智子がそう言うと、光恵が明日保育園に持って行ってほしい書類があるからと三人はもう一度病室に戻った。
病室に入ろうとした時、琴乃は病室の入り口にある患者の名札に目を留めた。
菊池千鶴…………。
まさか、こんな偶然が? 琴乃は信じられない思いで隣のベッドを覗くように声をかけた。
「すいません」
「はい」香穂が振り向いた。
「あのー、大変失礼ですが、間違えていたら申し訳ありません。菊池千鶴先生ですか?」
先生と呼ばれることが通常ではない情況で、しかもこんな若い人が、千鶴が先生であったことを知るはずもないことから、一瞬キョトンとする千鶴と香穂だった。
「どちら様でしょうか?」
千鶴が丁寧に尋ねた。
「ああ、ごめんなさい。私、野々村と申します。以前、野川で私の兄がちぃ先生の大変貴重なお話を伺ったと聞きまして。もしかと思いまして」
「ああ! 公平さんでしたね、お兄様は」
「はい。そうです!」
琴乃は人違いではなかったことを確認した。
「あの時の!」
香穂も驚きを隠せなかった。
「お兄様はお元気ですか? あの時はお兄様のお陰で私は助かりました」
千鶴は思いがけない琴乃との出会いに微笑んだ。
「はい。元気にしております。千鶴先生はいかがされたのですか? どこかお悪いのですか?」
「もう、年ですから、あちこちガタも来ますよ」
琴乃は笑顔を絶やさず話してくれる千鶴に温かさを感じた。
「母はもう一度公平さんにお会いしたくて野川に行きたがったのですが、体調を崩してしまいまして。でも公平さんとお会いしてから母の記憶はすっかり元に戻ったのです。本当に不思議なくらい」
「それはよかったですね。兄は相変わらず早朝のジョギングを続けています」
琴乃が千鶴たちと話していると智子が声をかけてきた。
「琴乃先生、お先に。明日またね」
「はい。お疲れ様でした」
智子は光恵とともに千鶴と香穂に軽く会釈をして病室を出て行った。
「そうそう、確かあなたは保育園の先生をしていらっしゃるのよね。公平さんから聞きましたよ」
「兄はそんなことまで話したのですか。恥ずかしいです」
「琴乃さんとおっしゃるのね。優しそうな可愛らしい先生ね。きっと子供たちの人気者なのでしょうね」香穂も琴乃の若さが眩しく思えた。
「琴乃先生はおいくつ?」
「二十三になりました」
「そう。私が国民学校の教員になったのは琴乃さんより若かったのね。二十歳だったのよ」
「兄からお話を伺いました。私なんか園児と同じくらいの精神年齢なのに、千鶴先生はすごいです。戦争を知らない私たちがどれほど思い巡らしても、千鶴先生が経験されたご苦労は到底思い及ばないものでしょうね」
琴乃は小学生と園児の違いはあるが、千鶴が教えていた年齢に近い今の自分が果たしてその時代の先生と同じように子供たちと接することができているだろうかと自問するのだった。
「それは仕方がないのよ。戦争という不幸な経験をすることになったからどうしようもなかっただけ。私だけが強かったんじゃないの。子供から大人まで耐えるしかなかった。だから、今の平和を若い人たちが守らなければならない。それができる人もまた強い人だと思うわ」
「千鶴先生、帰って兄に伝えます。そして、またすぐに兄と一緒にお見舞いに来ます」
「ありがとう。忙しいのでしょ、無理しないでね」千鶴は終始にこやかだった。
琴乃は公平を連れてくることを約束して病室をあとにした。
グラウンドでは大会の閉会式が行われていた。調布マリンズのメンバーの首には優勝の金メダルが輝いていた。雅也もメダルを手にすることができた。この優勝は雅也の人生において忘れることのできない感動であるに違いなかった。整列する選手の一人として並ぶ雅也を見て玲子も感動に包まれていた。
「雅也がまさか少年野球で優勝するなんて、まだ信じられません」
「子供の潜在能力ってすごいですね。今日は僕も興奮しました」
公平も雅也のひたむきさに敬意さえ感じていた。
グラウンドの中央では個人の各賞が贈られていた。
「続きまして、特別賞です。この賞は本大会で学童野球の最も大切な努力に対して贈られる賞です。今回、最後まで諦めないファイトを見せてくれた調布マリンズ、鈴木雅也選手に贈られます」
司会者から雅也の名前が呼ばれた。会場から大きな拍手が起こった。
「やったー!」公平が大きなガッツポーズをとった。
信じられないという顔で、雅也は帽子を尻のポケット入れると表彰台前に小走りで進んだ。
「表彰状、特別賞、鈴木雅也君、あなたは第三十五回調布市学童野球秋季大会にて素晴らしい成績を収めましたのでここに表します。平成二十○年九月二十六日、調布少年野球連盟会長安田浩吉、おめでとう」雅也は生まれて初めて表彰された。両手で賞状を受け取り、頭を下げた。その目から涙が乾いたグラウンドに落ちた。
閉会式が終わると雅也は母と祖母のところに走ってきた。
「おばあちゃん、このメダル、すごいやろ」
雅也が佳子の首に金メダルをかけた。
「本当によく頑張ったね。おばあちゃん、嬉しくて泣いちゃったよ」
佳子は孫の元気な身体を天に感謝した。
「本当に頑張ったな。俺も雅也から勇気をもらったよ」公平が称えた。
「野々村さん、ありがとうございました。野々村さんとお知り合いになっていなければ、この子はこんなに元気にはなっていなかったと思います。本当に何とお礼を申し上げればよいのか」
「いいえ、すべて雅也君の気持ちが勝ったからです」
佳子の孫に対する深い思いを感じながら、公平はその祖母のことが気になって仕方がなかった。
「ところで、雅也君のお祖母さん、先ほど調布のご出身と言われましたが、いつ頃のことなのですか?」
「昭和十九年までいました。太平洋戦争で本土の空襲が頻繁になってきた頃です。国民学校の一年生でした」
「失礼ですが、お祖母さんのお名前は何と……?」
「はい、佳子と言います」
「佳子……」公平は鳥肌が立った。
「間違っていたらすいません。佳子お祖母さんの旧姓は田所ではありませんか?」
公平はもしやとの思いから確認するように尋ねた。
佳子の顔色が変わった。
「そうです。旧姓は田所です。どうしてそれをご存じなのですか?」
佳子は驚きで声が上ずった。
「昭夫さんというお兄さん、そしてお母さんは邦子さんですね」
「はい。間違いありません。何故……どうしてそれを……」
「ちぃ先生……見つかりました……」
公平は興奮気味に誰に言うでもなく千鶴の名前を口にした。
「今、何とおっしゃいましたか! ちぃ先生と? 何故その名前を知っているのですか?」
佳子は目を見開いて公平に尋ねた。
「千鶴先生はご健在です。この調布に住んでおられるはずです」
「本当?……それは本当ですか!」
佳子は公平の言葉に目が泳いだ。
「はい。本当です。五ヶ月ほど前のことですが、偶然、菊池千鶴さんという戦時中に国民学校の先生だった方と知り合いました。そして、千鶴さんから調布の空襲の話を聞いたのです。空爆で調布も大きな被害を受け、多くの人々が傷つき、田所邦子さんもそのために亡くなられたことを。千鶴先生は昭夫さんと佳子さん兄妹のことを戦後もずっと気にかけてこられました。佳子さん、つまりお祖母さんが先生との別れ際に泣いたことを思い出すと今も胸が痛むと言っておられました。死ぬまでにもう一度、お二人に会いたいと。それだけを願って生きてきたと」
公平が出会いの経緯を簡単に話すのを聞きながら佳子は下唇を噛むように目を真っ赤にした。
「お会いしたいです。先生に会いたい……」
佳子は声を詰まらせ、ハンカチを目に当てた。
「おばあちゃん、どないしたん?」
雅也が心配そうに顔を近づけた。
「なんでもないよ。ちょっと昔を思い出しただけよ。心配ないから。ほら、お友達が向こうで待っているよ。早く行ってきなさい」
雅也がその場を去るのを待って、佳子はゆっくり話し始めた。
「昭和十九年の二月、寒い日でした。米軍の飛行機は本当に恐ろしかった。ちぃ先生は私たちを励まし、そして守ってくれました。ちぃ先生がいなければ私たちは恐怖で生きていけなかったと思います。私たち兄妹は母を亡くし、ちぃ先生に面倒を見てもらいました。先生が親代わりになって私たち兄妹を励ましてくれました。先生にさようならを言わなければならなかったあの日、今度は母となってくれた先生と別れなければならないのかと悲しみでいっぱいでした。ちぃ先生は何度も何度もごめんなさいと泣きながら言ってくださいました。気丈だった兄もちぃ先生と別れる日は泣きました。その後、兄は苦学をして中学校の教師になりましたが、昭和三十八年、父の遺骨収集のためにフィリピンに渡りました。父はレイテ島で戦死したと通知があっただけで、遺骨は戻ってきませんでしたから、兄は他の戦死された方々の遺骨も日本に戻したいと調査団に加わったのです。その後も、フィリピンで日本語を教え、生涯をフィリピンで過ごしました」
「では昭夫さんは……」
「はい。八年前にフィリピンで亡くなりました。肺がんでした。でも兄は幸せだったと言っていました。現地で家庭を持ち、現地で学校を作り、恵まれない子供たちを教えることが天職だといつも手紙に書いてきました。一度日本に帰国したことがあります。父の遺骨かどうかは分かりませんが、旧日本軍が大勢戦死した場所で拾い集めた遺骨を持ち帰って当時の名簿でできる限りの遺族に分骨をして差し上げました。そのまま秩父で暮らすことを勧めたのですが、マニラやダバオに待っている子供たちがいるからとフィリピンに戻りました。兄のつれあいや子供、孫がフィリピンにいるのですが、兄の意志を継いで、皆さん教育関係や日比友好架け橋団体などで立派に働いています。兄もちぃ先生との出会いがあったからこそ、その道を選んだのだと思います。ちぃ先生に逢わせてあげたかったです」
「お祖母さん、僕が必ずちぃ先生に連絡を取りますから、待っていてください」
公平は、もはやこの出来事がただの偶然とは思えなかった。公平は知らぬ間に運命の繋ぎ役となっていたのかもしれない。
夕方、公平が家に戻ると琴乃もちょうど帰ってきたところだった。
「お兄ちゃん! 大変!」
「こっちも大変だぞ」
二人ともその日の出来事を話したくて仕方がなかった。
「千鶴先生と会ったの!」と琴乃が言うのと同時に公平が言った。
「田所佳子さんと会ったんだ!」
お互い顔を見合わせたまま「今、何て言った?」
そして、おのおの、会った人のことを告げた。
「えー!」
「お前、どこで千鶴さんに会ったんだ?」公平から聞いた。
「それが偶然なの。今日、園長先生のお母さんが入院したって、グラウンドで言ったでしょ。あの後、智子先生と一緒にお見舞いに行ったの。そうしたらね、同じ病室に千鶴さんが入院していたのよ。もうびっくり。千鶴さんにご挨拶して、改めてお兄ちゃんを連れてくるって約束したの」
「そうか! ちぃ先生がいたか! なんてタイミングだ。もう偶然なんかじゃない」
「お兄ちゃんの方の大変は何なの?」
琴乃も公平の大変を聞きたかった。
「今日の野球の試合を見に来ていた雅也のお祖母さんが佳子さん、田所佳子さんだったんだよ。佳子さんは千鶴先生と別れて以来秩父で暮らして、たまたま息子さん家族が調布に引っ越してきて孫の雅也が調布の少年野球をするようになり、その応援で六十五年ぶりに調布に帰って来たんだ。驚いたよ。それで、千鶴先生の話になって、佳子さんも当時のことは悲しい思い出としてはっきりと覚えているんだ。ちぃ先生に本当に会いたがっているから、俺が必ず会わせますって約束したわけ。そしたら、お前が千鶴さんに会ったって言うから、なんて巡り合わせだろう」
「そうね。これも母さんのお導きかもしれないわね」
琴乃は公平の隣で笑う母の顔を見た。
翌日、公平はまず鈴木玲子に連絡を入れた。
「もしもし、野々村です」
「ああ、野々村さん、昨日はありがとうございました。昨晩はもう家族でお祝いでした」
玲子の声にはまだ昨日の試合の余韻が残っているようだった。
「あのー、佳子お祖母さんはご在宅ですか?」
「はい、今週はこちらにいる予定です。ちょっとお待ちください」
玲子はそう言うと佳子に取り次いだ。
「はいはい」佳子が電話口に出た。
「野々村です。佳子お祖母さん、見つかりました。千鶴先生が」
「えっ? もう見つかったのですか?」
昨日の今日である。佳子はまさかその連絡をもらえるとは思ってもいなかった。
「はい、偶然にも昨日、妹が千鶴先生にお会いしたのです。説明すると長くなるので、とにかく千鶴先生に会いに行きませんか?」
「ぜひお願いします」佳子も高鳴る気持ちを抑えきれない様子だった。
「では、三時に調慈会病院に来ていただけますか? 私も二時過ぎに仕事が終わり次第すぐに向かいますので」
「病院? ちぃ先生はご病気なのですか?」
「はい。詳しくは分かりませんが、ちぃ先生は入院されています」
「調慈会病院ですね。分かりました。必ず参ります。よろしくお願いいたします」
電話が切れた後も佳子はしばらく受話器を握りしめていた。目を閉じると幼い頃に見たちぃ先生の優しい笑顔が浮かび、佳子ちゃんと呼ぶ声が聞こえてきた。
公平は約束の時間よりも早く調慈会病院に着いていた。見舞いの受付で面会カードをもらうと首から提げた。予め琴乃から病室を聞いていたので病室はすぐに分かった。三時ちょっと前に佳子が玲子に付き添われて到着した。公平が面会カードを渡しエレベーターを待った。
「病室は五階の505号室です」
公平が佳子に病室を伝えたが、緊張から佳子は頷くだけで言葉を発することもできなかった。
「おかあさん、大丈夫?」
玲子も見舞いの花束を抱えながら佳子を気遣った。
「大丈夫よ」
エレベーターが五階に着いた。ナースステーションに505号室への見舞いであることを告げ病室に向かった。
「こんにちは。野々村です」
公平は左側のカーテン越しに声をかけた。
公平はベッドの背を立てて身体を起こしている千鶴とベッドの横でリンゴを剥いている香穂の姿を確認した。
「あらー、公平さん。わざわざありがとうございます。昨日、妹さんと偶然にお目にかかれて、本当に不思議なご縁。お母さん、公平さんが来てくださいましたよ」
香穂が笑顔で公平を迎え、その後ろにいた佳子と玲子に目を向け、軽く頭を下げた。
「お久しぶりです。ちぃ先生、お加減はいかがですか?」
「公平さん、ありがとう。またお会いできましたね。よかった」
千鶴も笑顔だった。
「ちぃ先生、素敵な方をお連れしました」
公平は佳子に前を譲った。
「…………」
千鶴はまじまじと佳子を見つめていた。六十五年という時間が巻き戻されたかのように千鶴の頭の中で蘇った。佳子も千鶴の顔を見て、若き日の千鶴の顔が重なった。
「ちぃ先生……」佳子はそう呼ぶのが精一杯だった。
「佳子ちゃん……なのね」
千鶴は幼かった佳子の面影をはっきりと重ねることができた。
「はい……」
佳子は千鶴の手を両手で包み込むように握った。
「佳子ちゃん! よかった、元気だったのね」
千鶴が佳子を抱きしめた。もう言葉は要らなかった。しばらく二人はお互いの存在を確かめ合うように抱き合って泣いた。
「ごめんね、ごめんなさいね。あなたたちを最後まで守ってあげられなかった。許してね」
千鶴は六十五年間言えなかった言葉を口にした。
「先生のせいじゃないです。あの時は仕方がなかった。でも、よかった、先生が元気で本当によかった」
「昭夫君は? 元気なの?」
「兄は八年前に亡くなりました。」
「えっ」千鶴は息を飲んで言葉に詰まった。
佳子は兄昭夫の生涯について説明し、最後にこう付け加えた。
「でも兄も、ちぃ先生のことを忘れたことはありませんでした。フィリピンでちぃ先生のような教育者を目指し、最期は家族に看取られて幸せだったと言ったそうです」
佳子の話に千鶴は顔を覆った。
「なんてことなの。辛かったでしょうね」
千鶴は胸が締め付けられた。
「兄はフィリピンの貧困地区で学校を作り、子供たちのために自分の人生を捧げることが天職だと言っていました。きっと、ちぃ先生ならどうするだろうかと思いながら教育者として生きたのだと思います。私たちは戦後、秩父に定住しました。母の墓も秩父の菩提寺に立てました。苦労はしましたが、兄妹で助け合いながらそれぞれに家族ができて、幸せに暮らしています」
「そうだったの。私も戦後、東京高等女子師範に編入して教師になったの。卒業してから仙台の高校で教鞭をとっていたのだけれど、調布にいた頃が懐かしいというか、やはり調布に戻らなければならないと思ってね、昭和四十年に亡くなった主人と一緒に帰ってきたのよ。いつかあなたたちに逢えると信じてきた。今日、願いが叶ったわ」
千鶴も佳子もお互いのその後のことと家族について多くを語り合った。
「ちぃ先生、これ覚えていますか?」
佳子は肩からかけていたポシェットの中から御守を取り出して見せた。
「もちろん覚えているわ。持っていてくれたのね」
「はい、どんな時も肌身離さず」
「私も佳子ちゃんにもらった御守を大事にしていたの。それがね……」
千鶴が説明をしかけた時、この話を聞いていた公平が横から口を挟んだ。
「えーっ? じゃあ、あの日、ちぃ先生が僕にくれた御守は……」
そう言いながら公平は鞄の中からその御守を取り出した。
「これです。これ」佳子が懐かしそう言った。
「実はね、あの日、昭夫君と佳子ちゃんとお別れをした日、私の持っていた御守を佳子ちゃんに渡したの。そうしたら佳子ちゃんも自分のお母さんからもらった御守を私にくれたの。そう、二人できっとまた会えるようにとお互いの御守を交換したの。でも、戦後の混乱で簡単に探すことはできなかったの。願いは叶いそうもないと思っていたわ。その時に会ったのが公平さん。あなただった。あの日、私はどうしてあそこに座っていたのか今でも分からないのだけれど、何故かしら、この御守は公平さんに渡さなきゃいけないって誰かが私の耳元で囁いた気がしたの。そうしたら、今日こうやって公平さんが佳子ちゃんを連れてきてくれた。この御守が私の代わりに公平さんと佳子ちゃんを引き合わせてくれたに違いないわね」
「そうだったのですか。ではもう僕がこの御守を持つ必要はないですね。大事な御守をお返しします」
公平は千鶴に差し出したが千鶴は公平の手を押し戻した。
「いいえ、これは公平さんが持っていてください。ねえ、佳子ちゃん」
「はい。公平さん、どうかお持ちになってください。お願いします。公平さんがいなければ、ちぃ先生とこうやってまた巡り合えることはなかったでしょう。母が導いてくれたのだと思います。本当にありがとうございました」
「でも、こうしてお二人は会うことができましたし、こんな大事な御守はやはり、ちぃ先生がお持ちになった方がいいんじゃないでしょうか」
「この御守はきっと一人が持っていてはいけないものなの。もし、将来、誰かのためにこの御守が必要となった時、公平さんが必要と思える人にまた渡してあげてほしいの。それがこの御守の持つ力だと思えてならないの」
その言葉は説得力のあるものだった。一連の繋がりは、ただの偶然が重なっただけなのかもしれない。しかし、公平も千鶴の言うことに説明のつかない力を感じるのだった。
「分かりました。ありがとうございます。大切にいたします。僕もこの御守に守られている気がします」
公平は御守を握る掌が温かくなるのを感じていた。
「ちぃ先生、それじゃあ、今度はこの御守を置いていきます」
それは公平がもらったものとまったく同じ御守だった。
「同じだ」
公平が千鶴子のベッドの上に二つ並べて置いた。
「これは兄の御守です。兄が亡くなって、フィリピンから私に送られてきました。兄の家族からでした。手紙によると、亡くなる前に兄が私に送るように家族に託したそうです。だから兄が守ってくれます。」
「佳子ちゃん、ありがとう。では昭夫君のご加護をありがたくいただくわ」
千鶴は拝むように両手でそれを受け取った。
「本当はもう一つ同じ御守があったはずなんです。母が持っていた御守です。でも母が亡くなった時、母は身に着けていなかったので、きっと、あの空襲でなくしてしまったのでしょう」
佳子は思い出すように語った。
その後、一週間、佳子は毎日病院に通った。そして、一度秩父に戻り、また来ることを約束した。
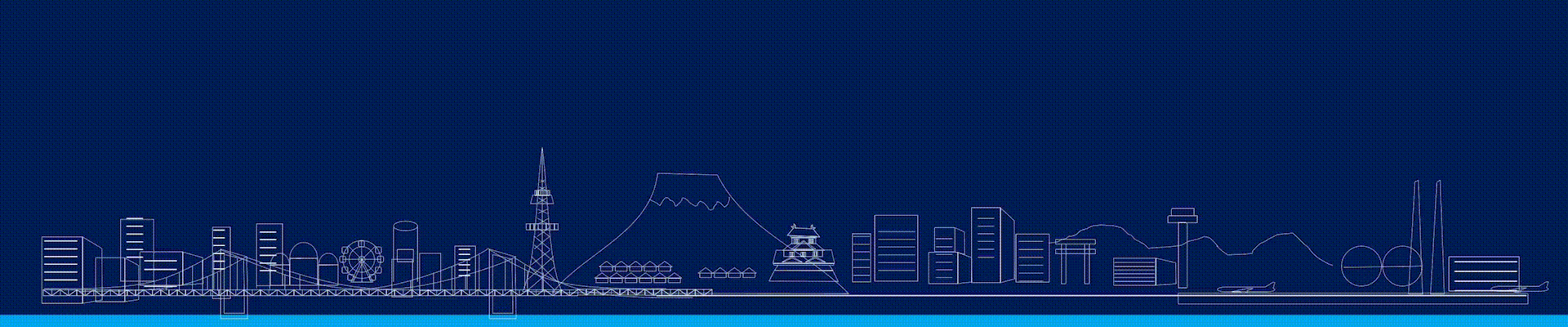







Login to comment
サインイン