門出
菊池千鶴の告別式に参列した公平は香穂から声をかけられた。
「公平さん、本日はわざわざお焼香いただきありがとうございました。母もいい顔で旅立つことができました。この一年、母は悲しい時代から平和で笑顔のある時代に至るまで、長い時間を凝縮して感じたのだと思います。公平さんのお陰です」
「僕ではありません。むしろ亡くなった千鶴先生があの日、私に声をかけてくださらなかったら、皆さんを結びつけることはできませんでした。千鶴先生こそが時空の神様だったのかもしれません」
「こんな日ですが、敢えて母のためにも教えていただきたいのですが、結婚式はお決まりになったのですか? 母に報告してあげたいので、もし、お決まりなら教えてください」
「はい。母の希望であった春に挙げようと思います。桜が咲く時期に」
「そうなの。お祝いさせてくださいね」香穂は嬉しそうに胸の前で両手を組んだ。
「ありがとうございます」
「あっそれから、これ」
香穂はあの御守を持っていた。そしてそれを公平に渡して言った。
「これを琴乃さんに渡してください。」
「どうしてですか? これは千鶴先生の形見だから菊池さんがお持ちになった方が」
「母が言っていたでしょ。この御守は必要とされる人に受け継いでいってほしいって。ですから、若い人に持っていてほしいんです。あの御守は人の絆を祈ったものです。だから公平さんと琴乃さんに持っていてほしいの。お願いです。受け継いでください」
香穂はそれが千鶴の願いだと公平に託した。
「分かりました。ではお預かりします」
「そう、受けてくださるの。ありがとう。母も必ず喜んでいるはずです」
「実は、美紗子の祖母が田所邦子さんからいただいたもう一つの御守を美紗子が受け継いだのです。これで三つ揃いました。必ず絆を大切にします」
公平は新たな気持ちで千鶴に誓った。
― 銀座 ―
KAZUMI Schokolade Haus がオープンした。
二百平方メートルほどの店内の、ガラスケースいっぱいにチョコレート菓子が並んだ。カラフルなもの、オーソドックスなものなど、その品数は百種類を超えていた。店の二階にはコーヒーラウンジが設けられ、店内で買い求めたケーキなどにパティシエが客の要望に合わせ、お気に入りのチョコレートプレートに文字入れをして提供するコーナーもある。
ベルギーからはバレンスタイン社の副社長がオープニングセレモニーのために来日した。開店前から外には長蛇列ができていた。美紗子は胸に金糸の花文字でKAZUMIと刺繍された黒のスーツに身を固め、客を迎える位置に立った。
中山圭太が開店の時間を知らせると大きなガラスの扉が開いた。客のお目当てはもちろんKAZUMIだった。品よく飾られた商品は飛ぶように売れた。
「すごい客の数ですね。このままだと午後に追加で入れないと品が途切れるかもしれませんね」中山圭太が嬉しい悲鳴を上げた。
「中山君の努力の賜物よ。ありがとう」
「やめてください、僕は青木先輩の指示通りに動いてるだけです。この店の成功は青木先輩の力です」
圭太は美紗子の言葉が嬉しかった。
「中山君は本当に物事を真っ直ぐに見ることができるのね。何度も準備段階で中山君のアドバイス助けられたことか。ありがとう。名は体を表すとは本当ね」
「なんですか、それ。俺の名前が何か示していますか?」
「だって、真っ直ぐじゃない。中山君の名前は。中山圭太、シンメトリーになっているでしょ。真っ直ぐに中心に一本筋が通っているっていうこと。これからもよろしくお願いします」
圭太は美紗子の言葉に照れるように、さあ、仕事、仕事と販売員のアシストに付いた。
外の列には公平と琴乃、そして深田幸樹が並んでいた。
「お兄ちゃん、銀座ってちょっと緊張するね」
「そうかぁ?」
「だってさ、セレブっぽい人が多いじゃない」
「それにしても高級感のある素敵なお店だね」と幸樹が感嘆した。
三人が店内に入る順番が来た。入り口で美紗子が待っていた。にこやかに深々と頭を下げたが、美紗子はさりげなく公平の手に触れた。そして、目を合わせ微笑んだ。
「いらっしゃいませ。本日はご来店ありがとうございます」
「美紗子姉さん、かっこいい」
「へへへへ、そう? 照れるな。琴乃ちゃん、後で二階に上がってきてね。幸樹さん、その節は本当にありがとうございました。お陰様で素晴らしいディスプレイができました。琴乃のことお願いしますね」
美紗子の丁寧な挨拶に幸樹は緊張した。
「はい。分かりました」大きな声だった。
「もう、恥ずかしい、大きな声で」
琴乃は叱るように言うと幸樹の腕を取って店内へと足を進めた。その様子に美紗子は安心の笑みを浮かべた。
「お兄ちゃん、見て。母さんのお菓子よ。これ」
琴乃はケースに並ぶKUZUKMIを見つめて悔やむように唇を噛んだ。
「母さんもきっと今日はここに来ていると思うよ」
「そうね」琴乃も公平の視線を追って天井を見上げた。
「野々村さんですか。初めまして。中山と申します。本日はご来店いただきありがとうございます。私、青木さんの下でこの店の商品企画を担当しています」
圭太にはまだ初々しさが残っていた。
「初めまして。野々村です。このたびはおめでとうございます。素晴らしいお店ですね」
公平は素直に開店を喜び祝福した。
「ありがとうございます」
圭太は公平を改めて見て、頭を掻きながら笑顔でちょっと悔しそうに言った。
「やっぱり負けだな」
「負け? どういう意味ですか?」公平は意味が分からなかった。
「実は僕、青木先輩に憧れていたんです。だから青木先輩と一緒に仕事がしたくてこのプロジェクトに転属願いを出したんです。でも、開業準備でポスターを作成した時に青木先輩には婚約者がいると知って、まるで失恋したように思って……やけ酒飲んだりして。へへへへ……、青木先輩が選んだ人ってどんな人だろうと想像していました」
「そうだったんですか。美紗子は僕にはもったいないくらいの女性です。今度遊びに来てください」
「はい。ありがとうございます」
圭太は軽く頭を下げると忙しそうに次の接客に回った。
公平たちは二階のコーヒーラウンジでそれぞれに選んだ菓子を囲んでいた。
「琴乃ちゃん、はい、これ」美紗子が白い化粧箱を持ってきた。
「お姉さん、何これ?」
「持って帰って。特別に今日だけお得意様への開店記念として準備したチョコレートのお菓子なの。琴乃ちゃんに一つとっておいたから」
「本当―? ありがとう。今晩楽しみ。お姉さんは何時頃帰れるの?」
「ごめんね、今晩はベルギーから来た幹部たちと会食なの。ちょっと遅くなるかも。なるべく早く帰るね」
「分かった。でも、最近、開店準備で疲れているんだから早く帰って休んでね」
「ありがとう。そうだ、公ちゃん、せっかく銀座に来たんだから、晩ご飯は深田さんと琴乃ちゃんにご馳走してあげてよ」
「あとで美紗子につけ回すからな」公平はそっけなく言った。
「お兄ちゃん、せこい!」琴乃が口を尖らせた。
らせん階段を中山圭太が小走りに上ってくると美紗子に囁くように言った。
「青木先輩、富士物産の鈴木さんがいらっしゃいました」
「ああそう。今降りていくわ。ごめんね、カカオの商社がお祝いに来てくれたようだからちょっと挨拶してくるね」
美紗子は三人にそう言うと階下に向かった。
コーヒーを飲み終えた公平たちは琴乃の希望通りに銀座を散策することにして席を立った。三人は階段を下り、売り場で仕事関係の人たちと話している美紗子に手で合図して出口に向かった。それを見た美紗子が急ぎ足で公平たちを追った。
「ごめんね、バタバタしていて、なるべく早く帰るね」
「うん、三人で食事して帰るよ。あの人は?」
「富士物産の食品本部長。今回のプロジェクトに特別に採ったカカオを調達してくれた人。ベルギーにいた時に何度も折衝して、あの方のお陰でいいカカオが入手できたの。今日はお祝いに来てくださったの。どうしてそんなこと聞くの?」
「いや、どこかで会ったような気がするんだけど、気のせいだよね。俺がそんな人知るわけないもんな。じゃあ、先に帰るよ。遅くなるようなら駅まで迎えに行くから電話しろよ」
「うん。分かった。今日は来てくれてありがとう」
美紗子の店を出た後も、美紗子と話していた商社マンのことが気になった。あの人は誰かに似ているんだけどな。公平はそれが誰なのか思い出せなかった。
二〇一二年、桜が満開となった四月、公平と美紗子、そして幸樹と琴乃は一緒に挙式の日を迎えた。美紗子の提案で二組同時に式を挙げることにしたのだった。
式場のチャペルには四人の招待客が大勢祝福に集まっていた。
四人を中心としてチャペルの階段で集合写真が撮られた。シャッターを切るのは藤堂保弘だった。集まった一人一人の自然な笑顔を藤堂はカメラに収めていった。それらは皆、平和を象徴するような笑顔だった。
「藤堂先生、お手伝いします」
真っ白いタキシードを着た深田が言った。
「何を言ってるんだ。今日はお前が主役じゃないか。琴乃さんを一人にするんじゃない」
藤堂は相変わらず深田の真面目さに呆れた。しかし、幸せいっぱいの深田に目を細めるのだった。
「先生、本当にありがとうございます。すべて先生のお陰です」
深田は深く頭を下げ、礼を言うと琴乃の傍に走っていった。
「琴乃先生、すごくきれいよ。なんだか泣けてきちゃうわ。深田さん、運動会の時はお世話になりまして、ありがとうございました。琴乃先生のこと、よろしくお願いしますね」
園長の土方光恵は琴乃の保護者のように話した。
「ありがとうございます。園長先生には本当にお世話になりっ放しで申し訳ないです。これからもよろしくお願いします」
「無理は言えないけど、少しでも長く保育園にいてね」
「はい。まだまだ私が卒園できそうもありませんから」
子供が大好きな琴乃は、保育園が天職だと感じていた。
「青木先輩、じゃなかった。野々村先輩、おめでとうございます」
中山圭太がワイングラスを捧げた。
「中山君、ありがとう。忙しいのにわざわざ来てくれて」
「店は任せて、ハネムーン楽しんできてください」
「もう私なんかいなくても中山君がマネージメントできるわね」
「まだ駄目ですよ。これからもビシビシお願いします」
中山圭太が一回り大きくなったように美紗子は感じた。
「野々村さん、おめでとうございます」
「ああ、上田さん。遠いところをありがとうございます。正代お祖母さんがお世話になります。いつも本当によくしていただいて、上田さんが傍にいてくださると思うと安心します」
「いやー、私みたいな者をご招待いただき感激です。久しぶりに東京に来ることができました。正代さんはお元気ですよ。昨日も若い人たちが頑張ってこの平和な日本をもっと平和にしてちょうだいって檄をとばされました」
上田も正代を担当して公平たちと知り合えたことが嬉しかった。
正代は車椅子だと周囲の人に迷惑がかかるからと式の出席を固辞した。しかし、公平はどうしても正代に美紗子のウェディングドレス姿を見せたかった。二人は式の前の週に正代には告げず上田の計らいで施設を訪れた。
「正代さん、美紗子さんが来られましたよ」
上田が部屋の入り口で声をかけた。正代は大きな窓から海を見つめていた。
「おばあちゃん、美紗子です」
その声に正代が振り向いた。そこには公平の腕に手を回したウェディングドレス姿の美紗子が立っていた。
「おばあちゃん、ありがとうございました。来週、私は公平さんに嫁ぎます」
美紗子は深々と頭を下げた。
「…………」
美紗子の姿を見た正代は言葉が出なかった。
「お祖母さん、ありがとうございました。美紗子をいただきます。必ず幸せにします」
公平も腰を折るように頭を下げた。
「公平さん、美紗子をよろしくお願いします」
正代はこぼれ落ちる涙を拭おうともせず二人を見つめた。
「深田君、素晴らしい結婚式だね」
「田辺社長、ありがとうございます。社長が私を拾ってくださらなければ今の私はありません。感謝しております」
「何を言っているんだね。君は今や我が社にはなくてはならない存在なんだから。従来のグラフの固定概念を刷新して写真を通じ情報を提供する新しい雑誌にしたのは君の力だ。これからも幅広くよろしく頼む。大いに期待しているよ」
田辺は深田を高く評価していた。
「ありがとうございます。今後も精進します」
「琴乃さん、深田が泣き言を言ったらお尻を叩いて送り出してやってください。お願いします」
「はい。承知いたしました。お任せください」
琴乃は最高の笑顔で応えた。
「公平さん、美紗子さん、本日はおめでとうございます」
菊池香穂が真っ赤なバラの花束を持って現れた。
「菊池さん、ありがとうございます。千鶴先生にも見ていただきたかったです」
「本当ね。でもきっと今日は、どこかでお二人のことを祝福していますよ」
「そろそろ一周忌ですね。お墓参りをさせていただきます」
美紗子も千鶴との出会いに感謝していた。
教会の中庭に用意された披露宴会場では賑やかに祝福の言葉が交わされた。公平と美紗子は腕を組んで客に挨拶をして回っていた。その時、公平が何かを思い出したように突然立ち止まり叫ぶように言った。
「あっ! そうだ! 雅也と雅人だ。あの人はあの兄弟に似ているんだ」
「なんなのよ、急に大きな声で。何の話?」
「あの富士物産の人だよ。どっかで会った気がしていたんだけど、そうじゃなくて、佳子さんの孫の雅也に似ているんだ」
公平のもやもやが晴れた。
「そう言えば苗字が同じ鈴木ね」
「えっ? そうなんだ。また奇跡か?」
「まさかね」
二人は同時にそう言うと顔を見合わせて笑った。
エピローグ
六年の時が過ぎた。
満開の桜が青空に美しく映えていた。公平と美紗子は五歳になった息子和馬を連れて野川を散歩していた。
風が吹いた。それは優しく三人を包むような風だった。公平はその風が母の化身であることを既に分かっていた。母さんも来ていたのか、和馬を見に来たんだろと心の中で呟いて微笑った。
「どうしたの? 嬉しそうね」
美紗子が公平と腕を組みながら言った。
「いや、別に」
公平は抜けるような青空を見上げた。そして、しゃがみこんで和馬に目線を合わせて言った。
「和馬、もし地震だとか大変なことが起こって、その時に父さんと母さんが和馬の近くにいなかったら、必ずここに来るんだよ。父さんも母さんも必ずお前を探しにここに来るから。いいな」
公平はその話が和馬にはまだ難しいと分かっていたが、風に揺れた桜がそれを言わせた。
「分かった。父さんと母さんがここに来るから僕もここに来ればいいんでしょ」
「そうよ。でも、お父さんは今、お前を探しに来るって言ったけど、正確にはお前たちよ。だって和馬はもうすぐお兄ちゃんになるんだから」
美紗子は大きなお腹をさすりながら優しく言って聞かせた。
「そうだな。もうすぐ弟か妹ができるんだから、和馬兄ちゃん、頼むぞ。ちゃんと面倒見てくれよ。そして弟か妹かまだ分からないけど、仲良くするんだよ」
「だいじょうぶだよ。でも、僕、妹がいいな」
和馬はお兄ちゃんになることが嬉しかった。
「なんで妹がいいの?」美紗子が聞いた。
「うーん、分かんないけど、きっとかわいいよね」
五つ違いの兄妹か。公平もそうなるような気がした。
「あっ! 琴乃叔母ちゃんだ。おばちゃーん」
和馬は向こう岸を前から歩いてくる琴乃を見つけて手を振った。
「あら、和馬! みんなで散歩? 私たちもそっちに行くわ、ちょっと待っていてね」
琴乃は夫幸樹と一緒に橋を渡ってきた。
「琴乃ちゃんもずいぶん大きくなってきたね」
「お姉さんと一緒の予定日なんて奇遇よね」
「きっと、おかあさんの仕業よ。二人いっぺんに見たいって言っているのよ」
美紗子と琴乃はお互いの新しい命にそっと手を当てた。
「そうだ、和馬。おばちゃんじゃなくて、おねえちゃんって呼びなさいって教えたでしょ」
「図々しいぞ、叔母なんだからおばちゃんだろう」
相変わらず真面目な幸樹が言った。
「いい? 和馬、他の人がいる時は、おねえちゃんって言うのよ。そしたらチョコレート買ってあげる」
「ほんと? 分かった。琴乃おばちゃん」
「もう、この子ったら」
千鶴はこうなることを予知したのだろうか。公平は御守を手にして思った。この御守は、あの戦争からいつか平和な世の中となった時に、人間の絆を継承してほしいと願う人々が公平に託したバトンだったのではないのだろうか。あの一連の不思議な出来事で時代の使者となった公平にはそう思えてならなかった。その小さな奇跡の連鎖がこの小さな野川の流れによって繋がった。それは野川に住む風水の神の仕業だったのかもしれない。
みんなの笑い声が野川に乗って流れていった。
あとがき
平成二十九年九月十五日、調布にある深大寺の白鳳仏(銅像釈迦如来像)が国宝に指定されました。深大寺は、天平五年(七三三年)に開創され、半世紀後にこの白鳳仏を本尊として迎えたと記されています。その悠久の歴史をもつ調布の地に住んで四十年、調布の良さを色々なところで感じてきました。
健康のためにと始めた野川沿いの早朝ウォーキング、毎朝見かける人達と朝の挨拶を交わすだけの一瞬の出会いがこの物語を生むきっかけとなりました。
この人達はどのような人生を歩んできたのであろうか、この人達はこれからどんな時間を過ごすのだろうか、そして、もしかしたら、この人達とどこかで縁があるのではないだろうか、そんな思いを巡らせながら野川を見てきました。四季毎にその様相を変える野川はきっと、行き交う人達の生き様を見てきたに違いありません。
古い記録では天平時代は勿論のこと、野川はもっと古くからその流れを止めていないのです。遣唐使が中国に派遣され日本が多くの文化を学んだ時代から、野川は流れていたのだと知った時、いったいこの川は何を見てきたのだろうかと想像を超える思いが頭を巡りました。古代の流れの傍には遺跡も発見され、川の水が生活には欠かせないものであったことを証明しています。古くから人は野川に守られ、そして野川を守ってきました。
そして現代に至り、人は今でも野川に憩い、いろいろな出会いを生んでいます。人々がこれからも絆を大切にし、野川が永久に平和の流れであってほしいと願ってやみません。
幅 舘 章
この物語はフィクションであり、登場人物も固有名詞もすべて架空のものですが、もし、偶然にも実在するものがあれば、それは野川の小さな奇跡の一つとしてとらえていただきたい。
《参考資料》
◆インターネットサイト
『調布市立図書館 市民の手によるまちの資料情報館』
『ボクの大東亜戦争 西澤和衛氏著』
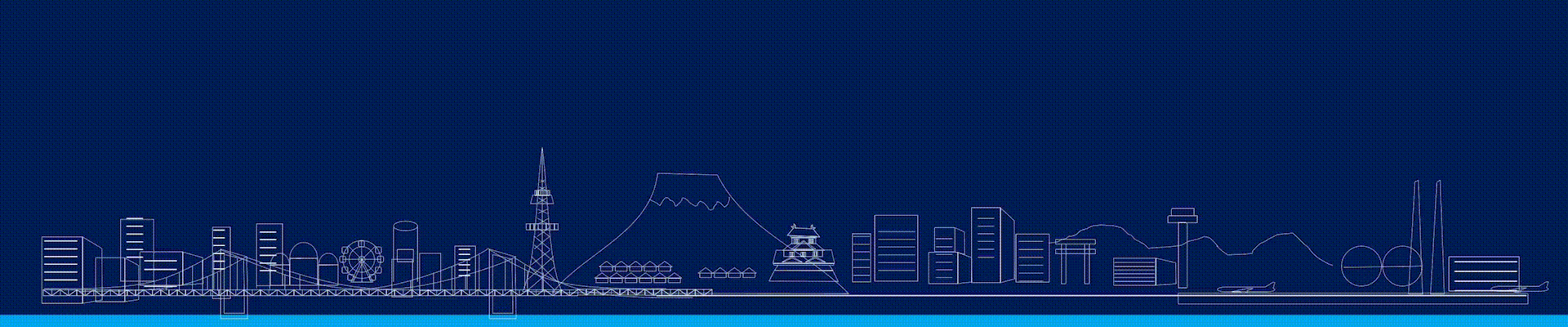







Login to comment
サインイン